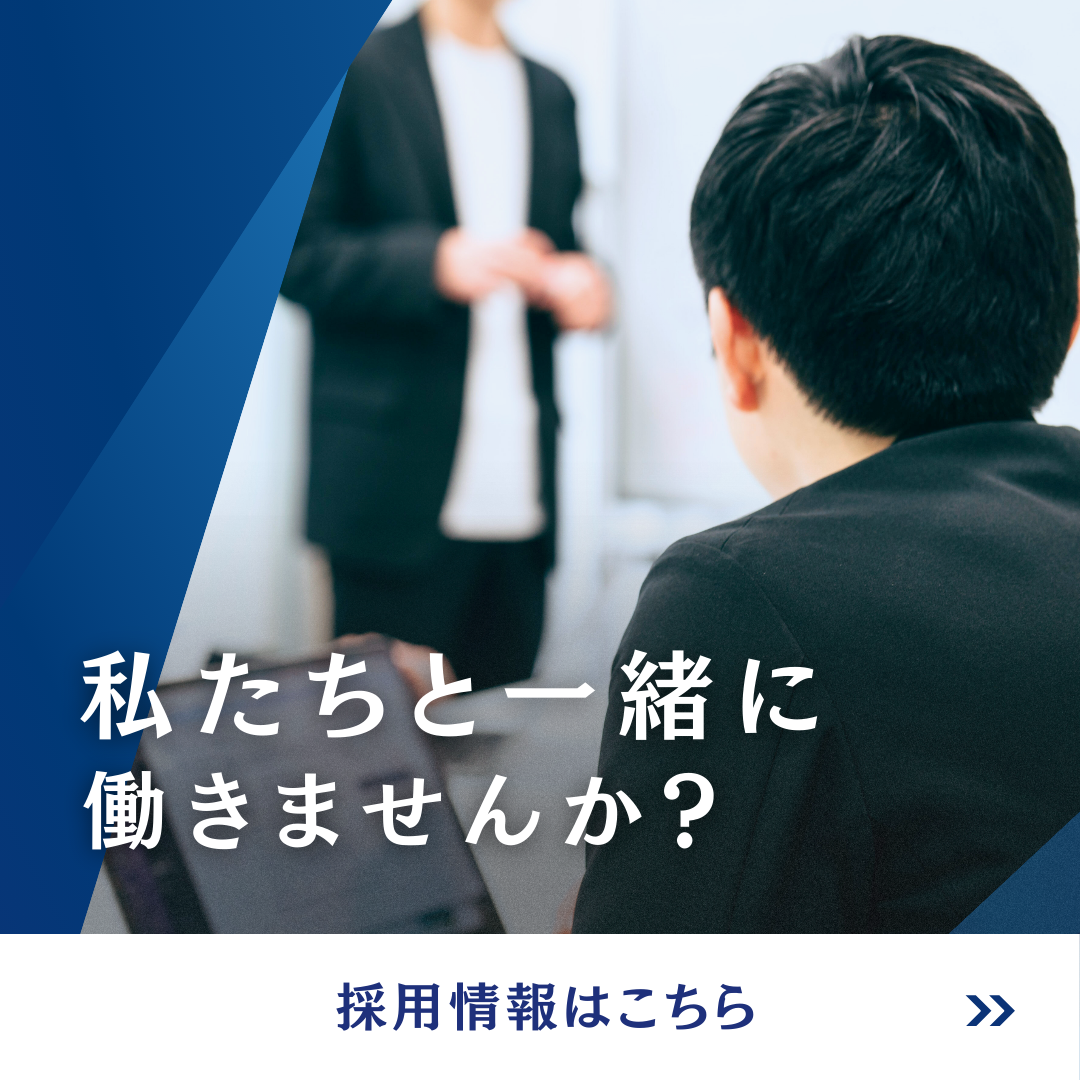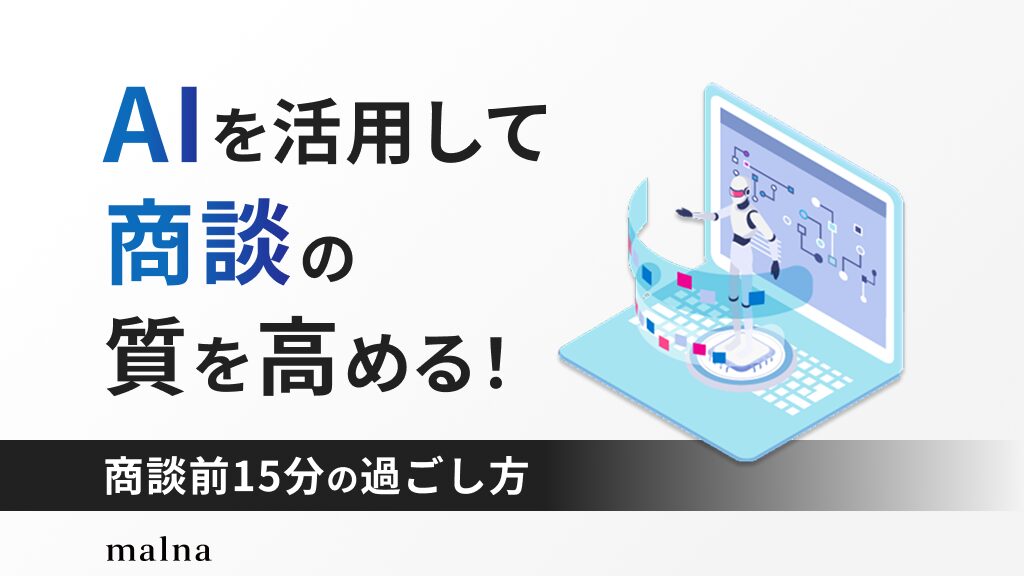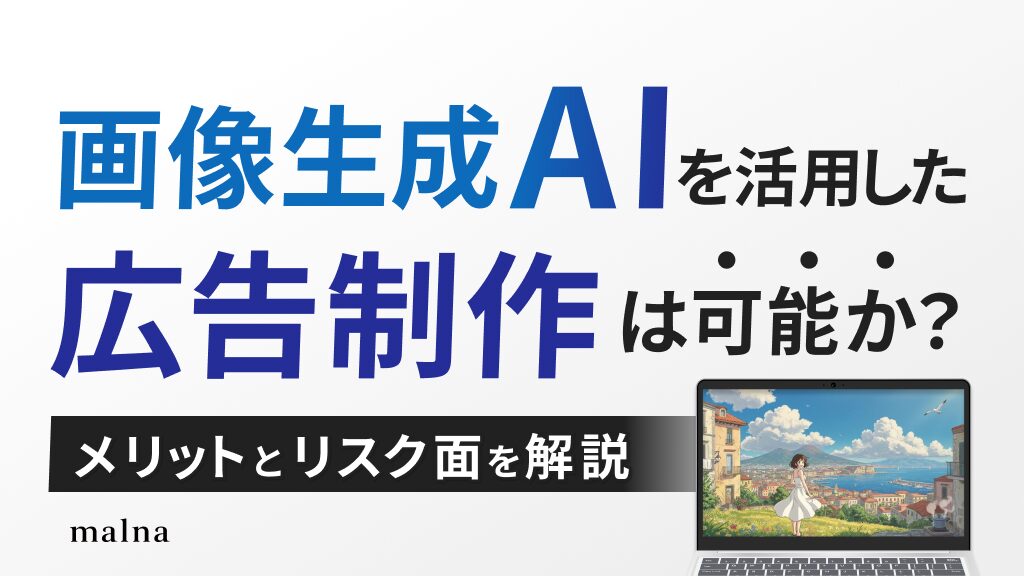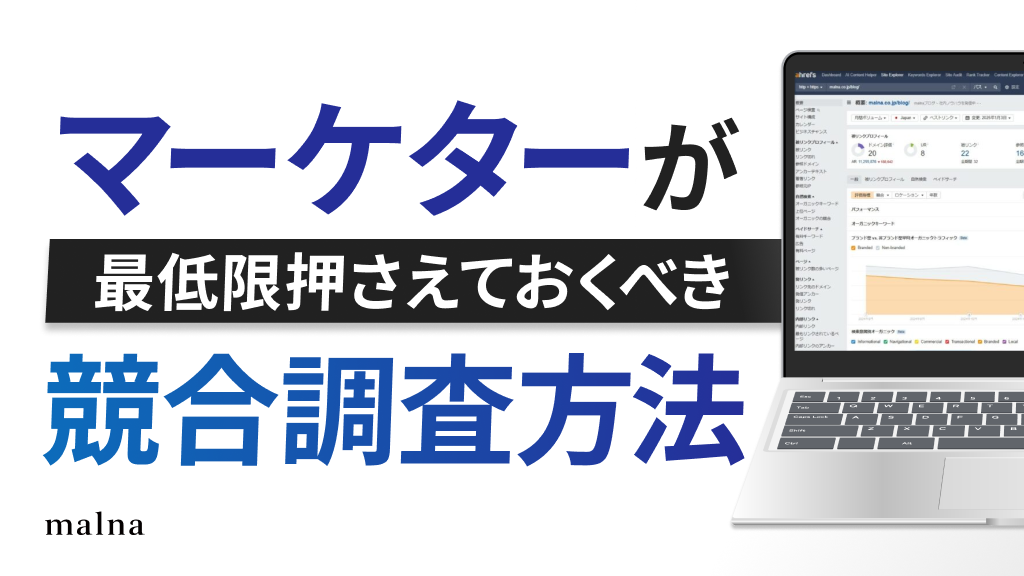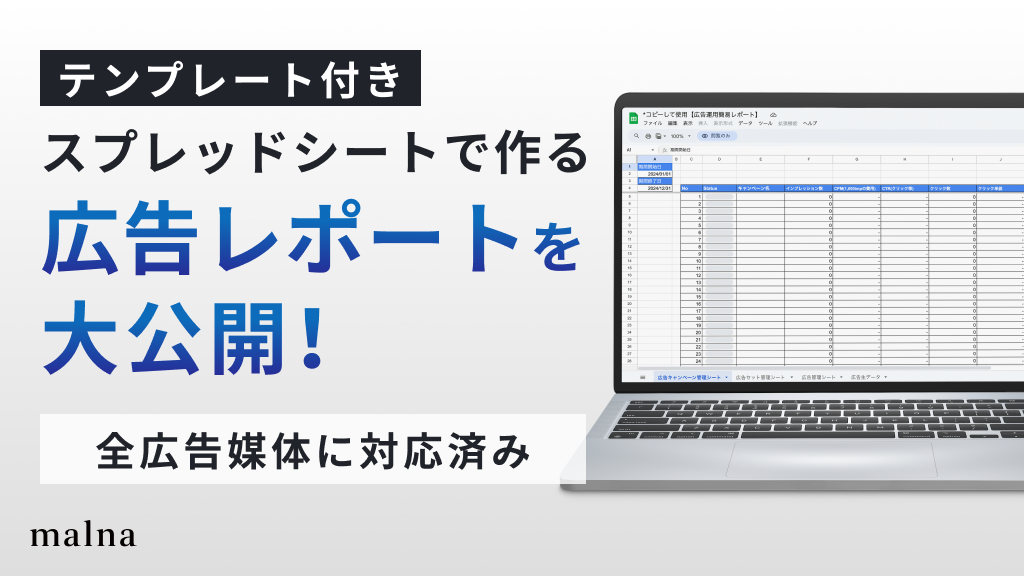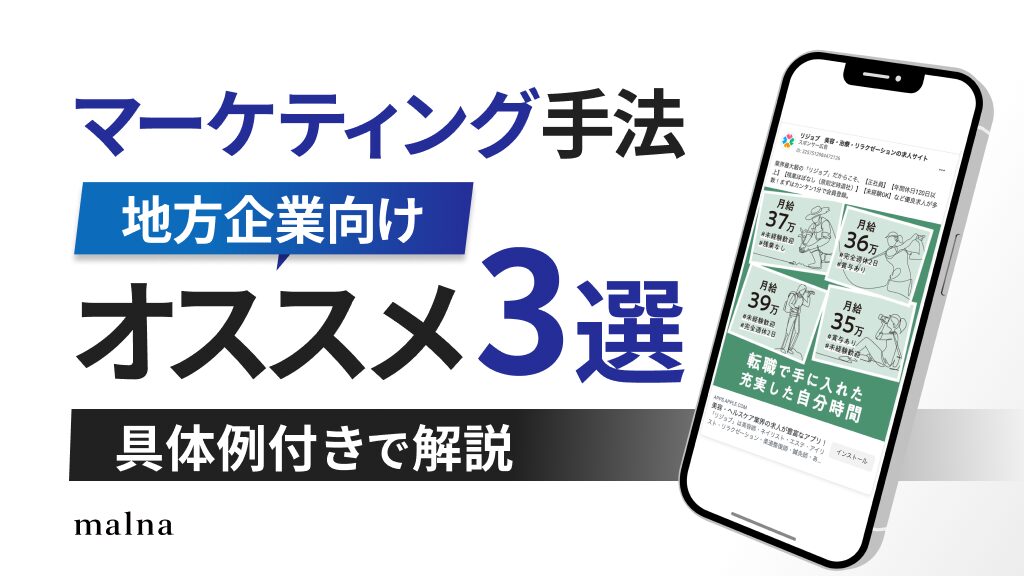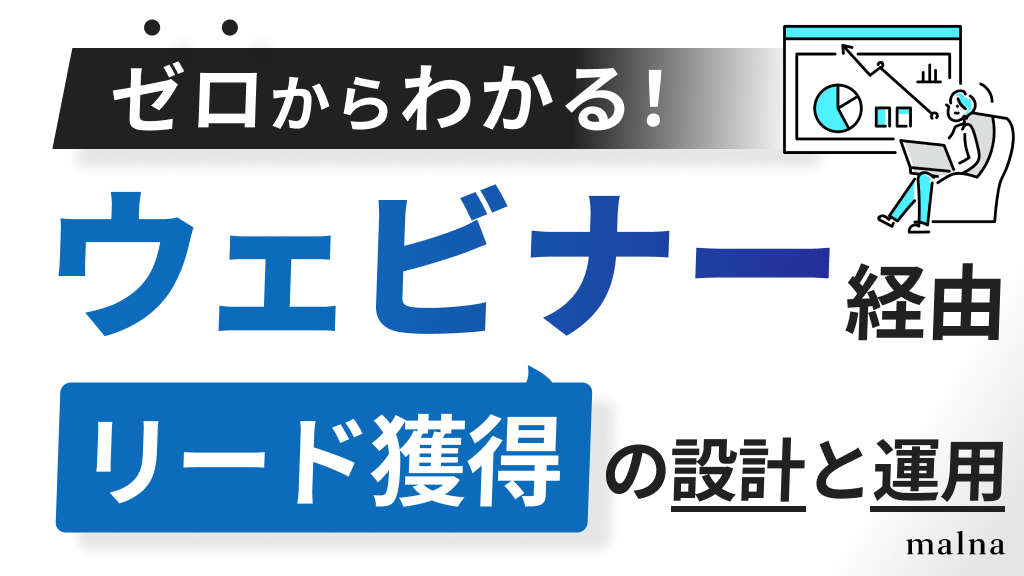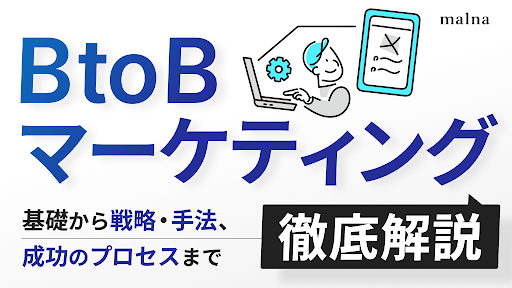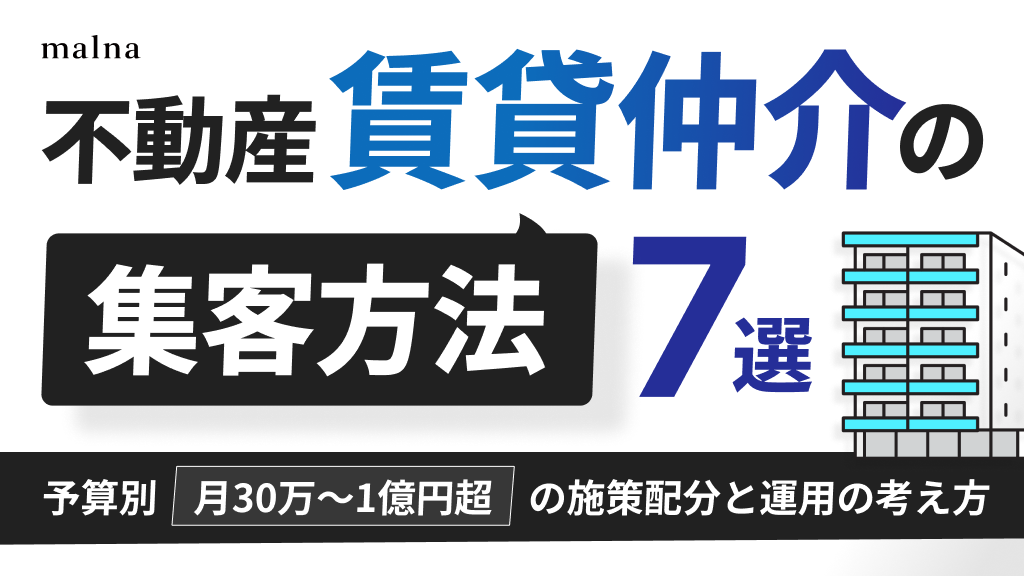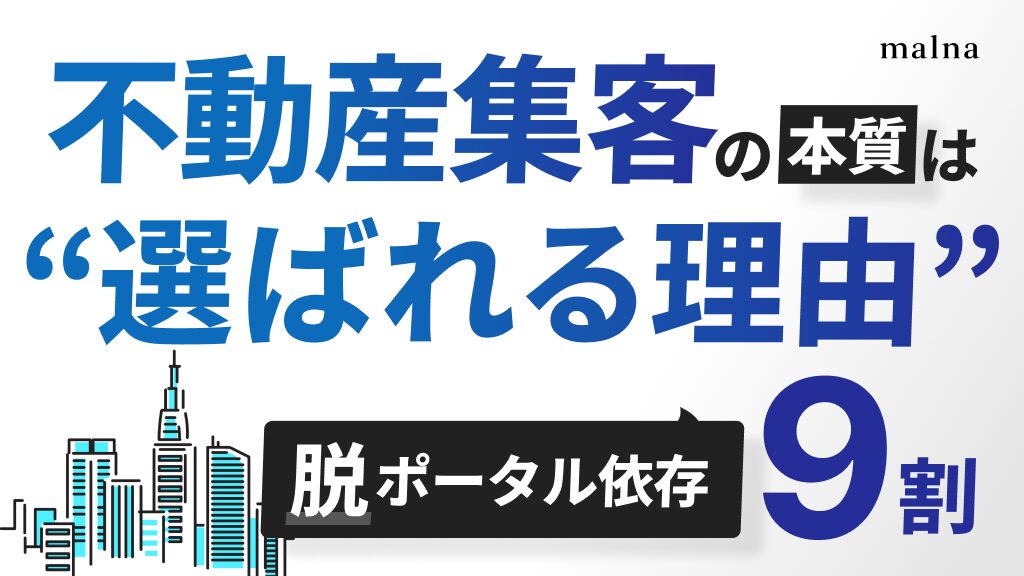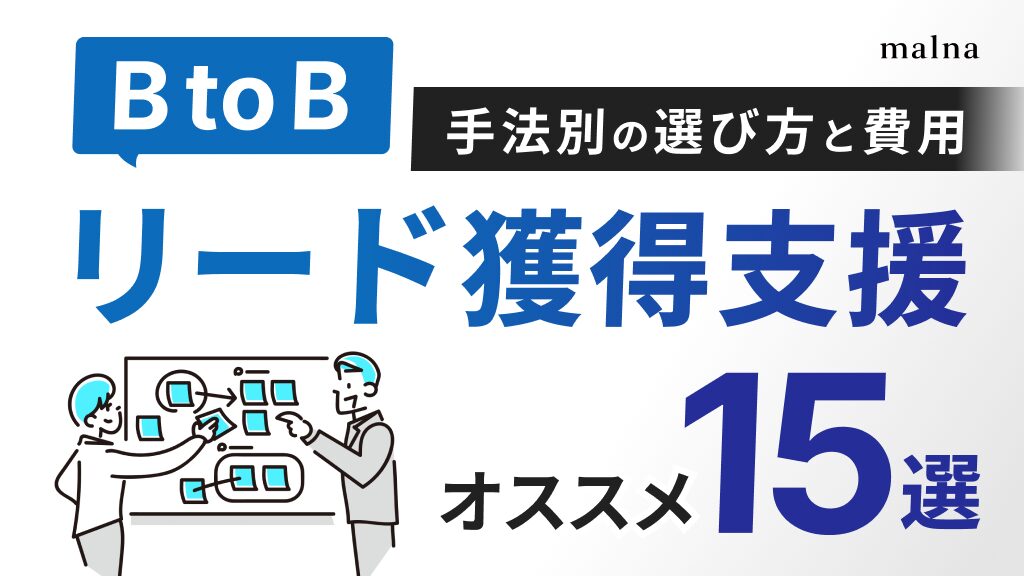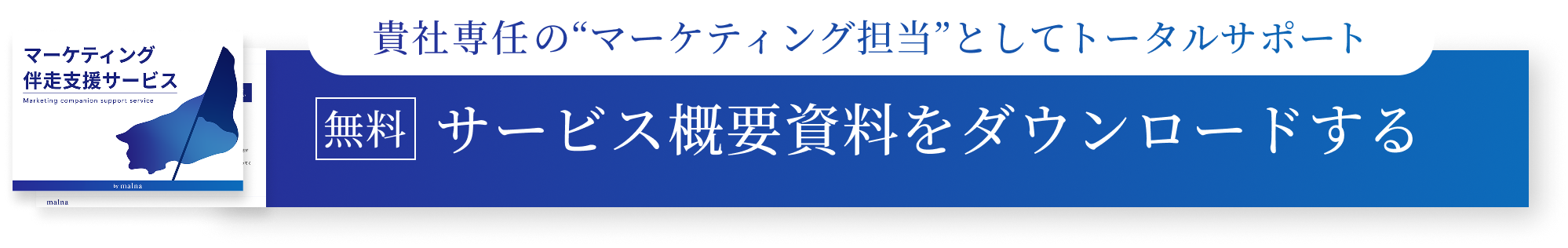2025.07.31
AIOは本当に意味ない?SEOとの違いやメリットなどを徹底解説
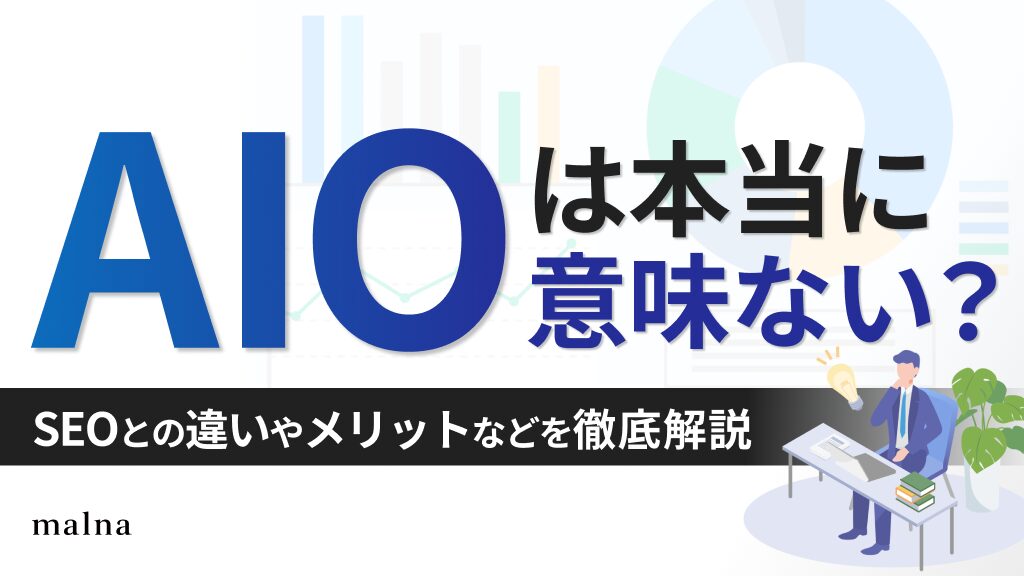
AIOは、ChatGPTやGoogleSGEといった生成AIの登場によって注目されています。今では、従来のSEO対策だけでなく、AIによる検索に対応するための新しい最適化も求められるようになってきました。
しかし一方で、「AIOは意味がない」「結局はSEOで十分」といった声があるのも事実です。実際、施策に取り組んでも成果が見えづらく、「何をすれば…」と感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、AIOとSEOの違いを整理しながら、AIOが持つ本来の役割やメリット、そしてAIに評価されやすくなるための実践ポイントをわかりやすく解説します。
AIOが本当に必要なのか、そしてどのように取り組むべきなのか、その判断材料を手に入れていただければ幸いです。
AIOが「意味ない」と言われる理由
AIOという言葉が注目を集める一方で、「意味がない」「効果が見えにくい」といった懐疑的な声も少なくありません。特に、SEOに慣れたマーケターにとっては、AIOへの投資や施策実行に対して慎重な姿勢が見られます。ここでは、AIOが「意味ない」と言われてしまう代表的な4つの理由について解説します。
AI選定基準が不透明で成果が測りづらい
AIOの最大の課題の一つが、AIがどのような基準で情報を引用するのかが明確でないことです。Google SGEやChatGPTなどの生成AIは、アルゴリズムや引用ロジックを一般公開していないため、どのようなコンテンツが、なぜ選ばれたのかが検証しづらくなっています。たとえば、FAQスキーマを実装したり、一次情報を充実させたりといった施策を行ったとしても、それがAIにどの程度影響しているのかが判断しにくいというのが実情です。SEOであれば、順位やCTR、CVなどで定量的に評価できますが、AIOにはそのような明確な選定基準がまだ確立されていません。
施策と成果の関係がつかみにくい
AIO施策は効果が出るまでに時間がかかるうえ、その成果を把握しにくいという点が意味がないと言われている1つの理由です。実施した施策の何が効果的だったのかを分析しにくく、それが理由でPDCAサイクルが回しづらいという課題もあります。たとえば、「構造化データを追加した」「タイトルの文脈を調整した」など複数の対応を同時に行った結果、どれがAIの評価に寄与したのかが分かりづらいため、継続的な改善の難易度が上がるのです。
「SEOで十分」という意見がある
特に、従来のSEOで安定した集客ができている企業や、BtoB領域でナーチャリング中心のマーケティングを行っている企業では、「AIOまでやる必要はない」という声もあります。SEOで上位を取れていれば、それで十分ではないか、と考えられがちですが、AIが要約中心の検索結果を提供するようになることで、ユーザーは検索結果のリンクをクリックせずに完結してしまう傾向が強まっています。つまり、いくら上位表示されていても、実際のクリックや認知に結びつかないリスクがあるのです。この「ゼロクリック時代」において、AIからの引用という新たな接点を確保することの重要性は、今後ますます高まると考えられます。
頻繁にコンテンツがアップデートされる
AIO施策の難しさは、AIの仕様や評価ロジックが頻繁に変化する点にもあります。Google SGEやChatGPTは日々アップデートされており、昨日まで引用されていたページが、ある日を境にまったく表示されなくなるケースも珍しくありません。この変化の激しさが、AIOが意味ないと捉えさせてしまう要因の一つです。SEOであれば、アルゴリズムアップデートに対する対応方針がある程度確立されていますが、AIOはまだノウハウの蓄積が進んでおらず、正解が見えにくい領域でもあります。そのため、リソースを割いたとしても、思ったような成果が出ず「やっぱり意味がない」と判断されやすいのです。
こんなAIOは意味がない
AIO対策を行えば必ずしも成果が出るわけではありません。むしろ、取り組み方を間違えると、かけた労力や時間が無駄になってしまう可能性もあります。本章では、実際によくある意味のないAIOの典型例を紹介し、どんな点に注意すべきかを解説します。
構造化されていないコンテンツ
AIが情報を引用する際に重視するのは「構造的な理解」です。段落が整理されていない、見出しが機能していない、文脈が曖昧な文章ばかりのページは、AIにとって内容を把握しにくく、引用する候補から外れてしまいます。特に、複数の話題がひとつの見出し内で混在している場合や、可読性が低いコンテンツでは、AIの読解を妨げてしまう可能性が高まります。
自動生成した“AI文章”
近年では、ChatGPTなどを活用して短時間で大量の文章を生成する手法も一般化していますが、これだけでは意味のあるAIOとは言えません。自動生成された文章は、他サイトと内容が似通いやすく、独自性や一次性に欠けることが多いため、AIによる引用の対象としては弱くなります。人間の視点が反映されていない文章は、AIにも「価値が低い」とみなされがちです。
ユーザー視点を欠いた情報を羅列
AIOで重視されるのは「ユーザーの課題をどれだけ的確に解決できるか」です。そのため、単なる用語の羅列や一般論だけで構成されたコンテンツは、AIにもユーザーにも響きません。たとえば、FAQ形式であっても、実際の質問に即しておらず、想定読者の悩みに答えていない場合は意味が薄れます。読者が「これが知りたかった」と思える具体性が求められます。
更新性がなく、古い情報のまま放置されたページ
AIはコンテンツの新しさや最新性も評価要素に含めています。数年前に書かれたまま一度も更新されていない情報は、いくら内容が良くてもAIから見て古い情報源とみなされ、引用されにくくなります。特に、制度や仕様が頻繁に変わる業界では、定期的なアップデートが欠かせません。最新の日付が記載されていない記事や、古い統計データだけを使っているページも注意が必要です。
意味のあるAIO対策5選
では、どのようにすれば「意味のあるAIO対策」になるのでしょうか?ここでは、AI検索に対応した効果的なAIO対策について、実践的な観点から具体的なポイントを解説していきます。
読者ニーズに基づいた、質の高いコンテンツにする
AIOで成果を出すための第一歩は、「誰に、どんな課題解決のために情報を届けるのか」を明確にすることです。AIは単なるキーワードの羅列よりも、明確な問いに対する分かりやすい答えを高く評価します。したがって、FAQ形式や、章末に要点をまとめたサマリーの挿入など、読者の意図に合った構成が有効です。特に、検索意図が明確な「○○とは?」「○○のやり方」などに対して、簡潔で構造化された回答を提示することで、AIがその情報を「引用にふさわしい」と判断する可能性が高まります。曖昧さを避け、読者の課題を的確に捉えたコンテンツ作成が、意味あるAIOの土台となります。
一次情報や独自の視点を盛り込む
AIに引用されるコンテンツの特徴として、独自性と一次性の高さが挙げられます。実際に体験した事例や、企業独自で収集・分析したデータ、専門家へのインタビューなどは、他にはない価値ある情報としてAIにも高く評価されます。また、単に情報をまとめただけのコンテンツではなく、「その企業や筆者ならではの視点や解釈」を含めることで、より信頼されやすくなります。とくに専門性が求められる業界や領域では、引用される可能性が高まるため、積極的に取り入れていくことが有効です。
E-E-A-Tを意識したコンテンツ設計を行う
AIは単に情報が正しいかどうかだけでなく、「誰が書いているか」「その情報はどれだけ信頼できるか」も重視します。これはGoogleが提唱するE-E-A-T(Experience,Expertise, Authoritativeness,Trustworthiness)の考え方とも一致しており、AI検索においても重要な基準となっています。具体的には、記事に著者名とプロフィールを記載する、専門資格や実務経験を明記する、出典元をリンク付きで示す、などが挙げられます。これにより、AIからの引用だけでなく、ユーザーからの信頼性も高まるため、一石二鳥の効果が得られます。
人間による読みやすさを意識する
AIに最適化されたコンテンツとはいえ、最終的に読むのは人間です。つまり、「人が読んで理解できる文章であること」が大前提となります。冗長な文や抽象的な表現を避け、文の長さを適切に整え、箇条書きや図表も活用して視認性を高めましょう。見出しや段落構成も整理されていることで、AIは構造を理解しやすくなり、引用の精度が上がるとされています。「人にもAIにもわかりやすい」ことが、意味のあるAIOの鍵です。
AIに読み取られるための技術対策
AIO対策では、コンテンツの中身だけでなく、「AIに正しく読み取られる環境づくり」も欠かせません。どんなに質の高い記事でも、構造が不適切だったり、技術的な最適化が不十分だとAIに引用される可能性は低くなります。まず、HTMLの見出しタグ(h2、h3など)を正しく使って情報を整理し、AIが構造を理解しやすいページを設計することが重要です。加えて、Schema.org対応の構造化マークアップを活用すれば、FAQや記事構成が機械的に把握されやすくなり、引用の可能性も高まります。そのほかにも、ページ表示速度の改善、モバイル対応、不要なURLの整理といった施策がAIにとっての「読みやすさ」を高める要素です。
AIOのメリットとデメリット
AIOは、正しく取り組めばAI検索における可視性向上やブランド認知の獲得につながる有効な手段です。一方で、従来のSEOとは異なるアプローチや技術的な知識が求められるため、実装にハードルを感じる方もいるでしょう。このセクションでは、AIOのメリットとデメリットを整理して紹介します。
メリット
AIOには、AI時代の検索環境において新たな価値をもたらすさまざまな利点があります。ここでは、特に重要な3つのメリットについて解説します。
AIに引用されることで“ゼロクリック”でも認知が得られる
生成AIによる検索結果では、ユーザーがリンクをクリックせず、AIによる要約や引用だけで疑問を解決する「ゼロクリック検索」が増加しています。AIOによりAIに自社情報が引用されることで、クリックされなくてもブランド名やサービス名がユーザーの目に触れる機会が増え、間接的な認知獲得が可能になります。たとえば、ChatGPTでの回答文中に「◯◯社の調査によれば〜」といった形で言及されれば、クリックなしでもユーザーに印象を残すことができます。このように、AIOはこれまでリーチできなかった“検索ユーザー以外”への新たな認知機会を創出する手段としても注目されています。
ユーザーにもAIにも伝わる情報設計でコンバージョン向上
AIOでは、情報を構造的かつ明確に整理することが求められます。この結果、AIだけでなくユーザーにとっても「わかりやすく」「必要な情報にすぐたどり着ける」コンテンツになります。結果として、ユーザーの行動喚起(例:資料請求、問い合わせ、購入)につながりやすくなるというメリットがあります。また、FAQ形式や箇条書き、図表を適切に配置することで、読みやすさや理解のしやすさが向上し、ユーザー体験(UX)全体の底上げにもつながります。こうした構造化と視認性の高い設計は、CV向上にとどまらず、長期的な顧客関係の構築にも繋がります。
対策強化により、コンテンツ品質が向上
AIOを意識したコンテンツ制作を行うことで、自然と情報の構造化や一次情報の追加、信頼性の強化などが行われるため、結果として記事の品質そのものが向上します。これはSEOにおいても高く評価される要素であり、検索順位の向上や他コンテンツへの好影響も期待できます。つまり、AIO対策はAI検索における対策にとどまらず、全体のコンテンツ力を底上げする効果があるのです。長期的な資産となる高品質コンテンツを増やすためにも、AIOの視点は有効に機能します。
デメリット
一方で、AIOにはいくつかの注意点も存在します。特にリソース面や可視化の難しさは、実践において障壁となるケースが少なくありません。
実装・設計の難易度が比較的高い
AIOでは、FAQスキーマの設定や構造化マークアップ、情報の文脈整理など、ある程度のテクニカルスキルや設計力が必要になります。また、マーケターだけでなく、エンジニアやデザイナーとの連携も求められるため、プロジェクトベースでの体制作りが必要なケースも多く見られます。特に中小企業や少人数のマーケチームでは、こうした実装工数を確保するのが難しいという課題があります。そのため、まずは簡単に取り組めるFAQ形式や見出し構造の見直しから始めるなど、段階的な導入が現実的な進め方と言えるでしょう。
効果が可視化できない
AIOの成果は、SEOのように順位やCTRで明確に測れるわけではありません。AIに引用されたとしても、Google AnalyticsやSearch Consoleでは詳細な可視化が難しく、施策の効果が実感しにくいと感じる方も多いです。現在のところ、引用されたかどうかを定期的にAI検索で手動チェックする、ChatGPTでブランド名を検索する、といった手法が主流ですが、確実かつ定量的なレポート手段がない点は、今後の改善課題といえるでしょう。このような不透明さから、社内での成果報告や投資対効果の説明が難しいという声も少なくありません。
短期でのCVは期待値が低い
AIO対策は、即効性のある施策ではありません。広告運用のように、設定をすればすぐに流入やコンバージョンが発生するものではなく、コンテンツの最適化がAIに評価されるまでには時間がかかります。また、たとえAIに引用されたとしても、そこから直接コンバージョンにつながるとは限らず、成果が数字として見えてくるまでに一定のタイムラグが生じます。特にBtoBや高単価商材のように、検討期間が長い商材では、AIOによる間接的な認知向上や信頼構築が徐々に効いてくる形になるため、短期的なCVをKPIに据えると「効果がない」と判断されやすくなるリスクがあります。
成果が生まれるまでに運用コストがかかる
AIOは一度対策を施したら終わりではなく、AIのアルゴリズムや評価基準が変化するたびに、構成や情報の見直しが必要になります。Google SGEのアップデート、ChatGPTの挙動の変化、検索画面レイアウトの変更などがあれば、引用されるコンテンツも変わる可能性があるため、継続的な運用が求められるのです。その点で、リスティング広告やSNS広告のような「出稿してクリックされれば成果につながる」モデルとは大きく異なります。だからこそ、AIO施策を検討する際は「継続できる運用体制かどうか」「現状のリソースで実行可能か」といった観点から、段階的に導入する計画を立てることが重要です。
AIO対策には一定の時間とコストがかかる
AIOは、成果につながる可能性がある一方で、短期的に簡単に実現できるものではありません。構造設計や専門性の担保、技術的対応など、複数の要素が絡み合うため、ある程度のリソースと時間が必要です。ここでは、AIOを無理なく行っていくために意識したい3つのポイントを紹介します。
1. すべての改善施策に対応するのは非現実的
AIOでは、構造化マークアップ、FAQ設計、著者情報の記載、一次情報の挿入、E-E-A-Tを意識した構成など、求められる要素が多岐にわたります。ただし、それらをすべて均等に実行するのは難易度が高く、リソース的にも厳しいというのが実情です。業界やコンテンツの種類によって効果の高い対策は異なるため、「まず何から始めるべきか」を見極めることが重要です。すべてを一斉に始めるのではなく、インパクトの大きい箇所に的を絞って進めることが、効率よく成果を上げるための基本戦略です。
2. 改善し続けることを前提に設計する
一度設定しただけで効果が続く施策は少なく、多くの場合で運用や更新が求められます。施策ごとの導入時の負荷や、その後の維持にかかる労力をあらかじめ把握しておくことで、現実的に続けられる体制を作ることができます。以下の表は、主要なAIO施策について「初期工数」「継続工数」「特長」を比較したものです。
無理なく継続できる方法を見つけることで、AIOの取り組みが一過性に終わらず、長期的に成果へとつながります。
3. 自社にフィットする施策を選び抜く
限られたリソースの中で成果を出すためには、「やるべきこと」に絞って行動する判断力が重要です。施策の汎用性や業界特性をもとに、優先順位を見極めて取り組むことが成果への近道となります。たとえば、AIによるFAQ表示が多い業種では、FAQページの精度向上が直接的な効果を生みやすいです。逆に、専門性や信頼性が重視される領域では、著者や監修情報の提示が強い武器になります。また、他社と差別化できる独自データの提示も有効な選択肢の一つです。重要なのは、「やれること」ではなく「やる意味があること」に集中することです。効果の見込める分野に優先的にリソースを配分することで、効率よくAIに引用される土台を築くことができます。
まとめ
AIOについて、意味がないと言われる理由から実際に意味のあるAIO対策やAIOのメリットデメリットについてもまとめ、解説してきました。AIOで求められる多くの施策は、いずれも本来のSEOでも重視されていた内容です。つまり、SEOでも重要視されていた内容をAIにとってもわかる形で行うというのが、AIOの本質だと言えるでしょう。ただし、すべてのAIO施策に一律で取り組む必要はありません。
業種やマーケティング戦略によって、AIからの引用を狙う意義や優先度は異なります。たとえば、toBでのナーチャリングが中心のビジネスでは、検索からの直接流入よりも信頼形成が重視されるため、E-E-A-Tを意識したコンテンツ設計が有効です。一方で、toCの比較系コンテンツであれば、FAQ構造やページスピードの最適化が成果に直結する可能性があります。つまり、意味のあるAIOとは、自社の目的やリソースに照らし合わせたうえで、優先順位をつけて取り組む最適化活動だと言えるのです。
もし今、「SEOで結果が出せていない」「AIOにも対応したいが、リソース不足などで体制が整っていない」といった悩みを感じているなら、一度malnaにご相談ください。malnaでは、SEOとAIOの両面から成果に直結するコンテンツ設計・運用の支援を行っています。ChatGPTやGoogle SGEへの対応に向けたコンテンツ改善、構造化支援、編集体制の見直しなど、現状の課題にあわせた実践的な提案が可能です。
AIOは単なるトレンドではなく、今後の検索体験における基盤づくりとも言えます。だからこそ、戦略的に、無理なく、意味のあるAIO対策を始めていきましょう。
無料相談はこちら 記事一覧はこちら- malnaのマーケティングについて
-
弊社ではメディアやSNSなど総合的な支援が可能です。
媒体ごとに違うパートナーが入ることもなくスピーディな意思決定が可能です。
ご不明点や不安な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 - サービス資料はこちら 詳しく見る