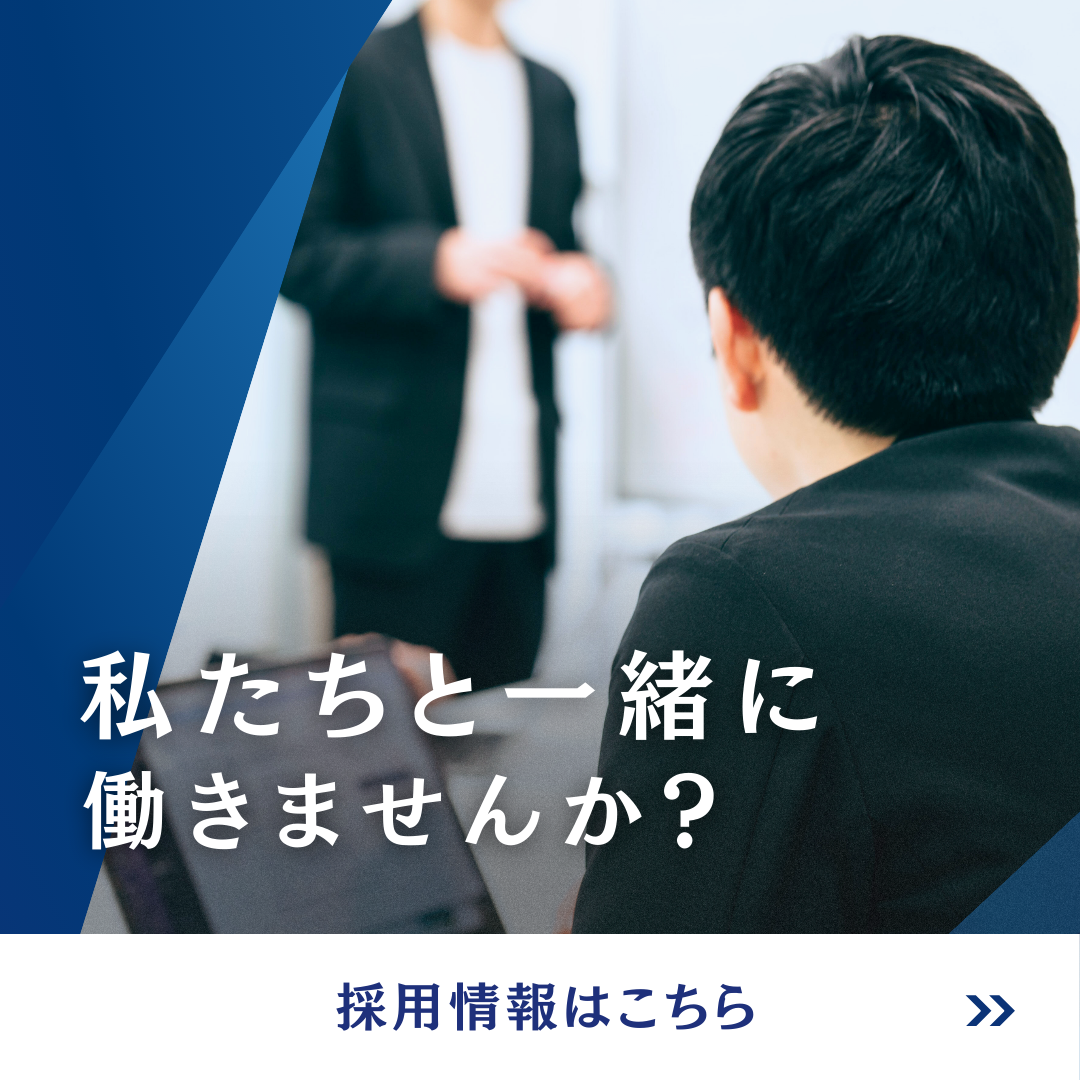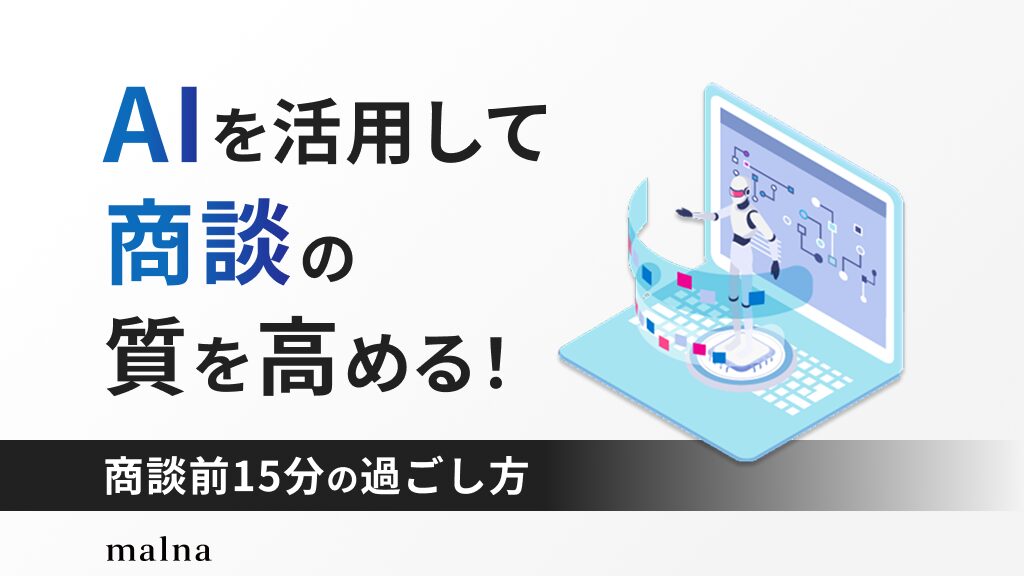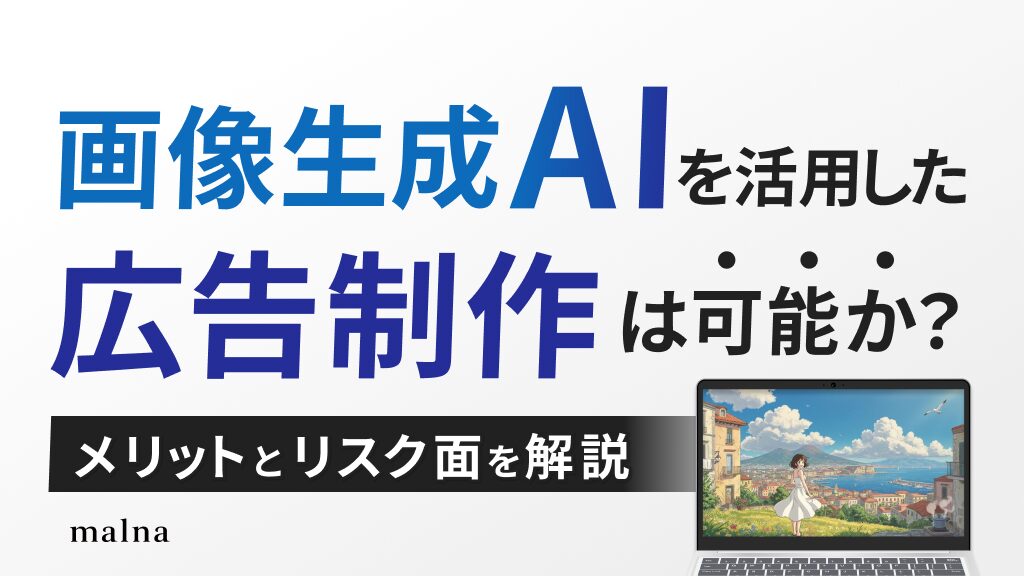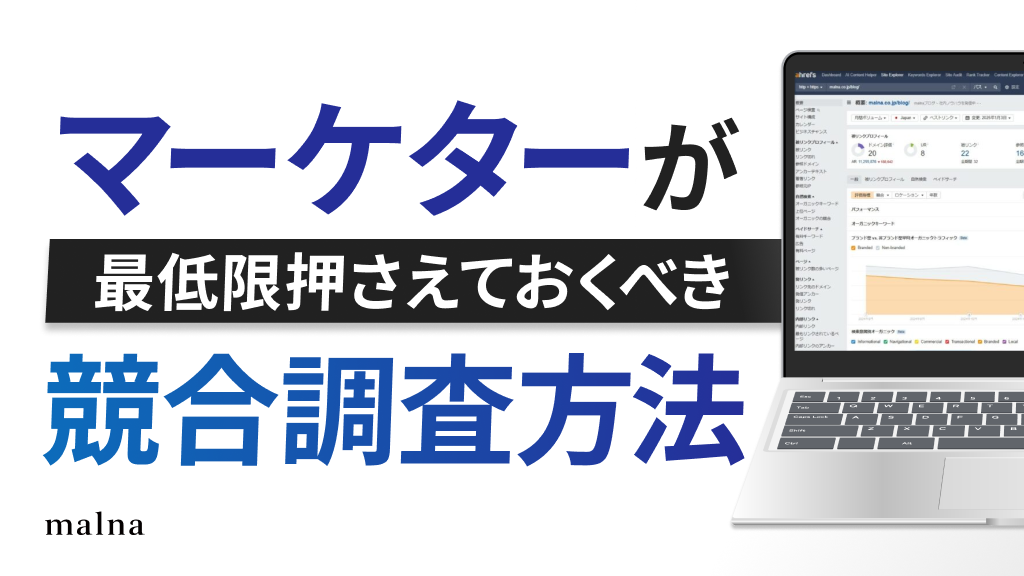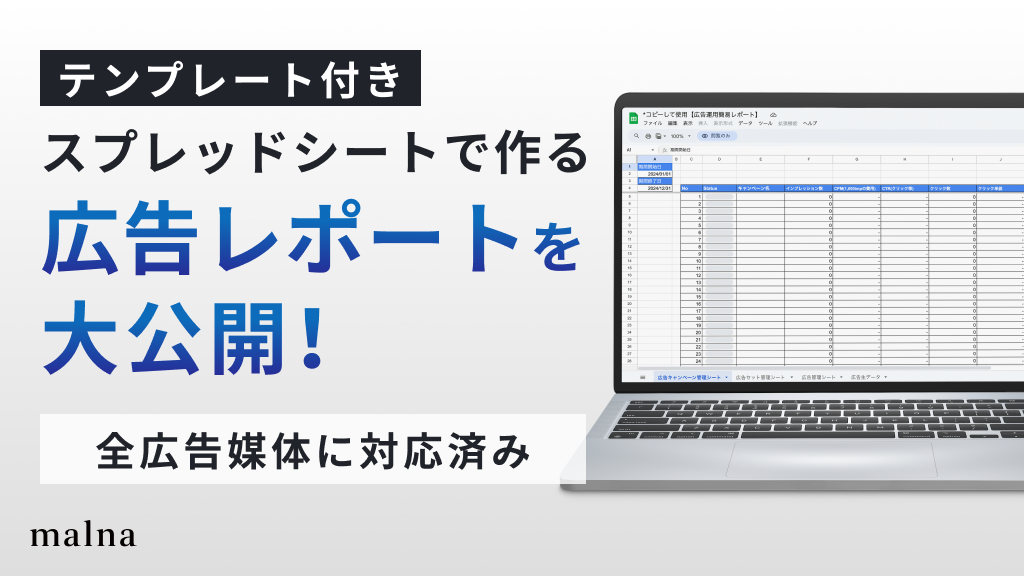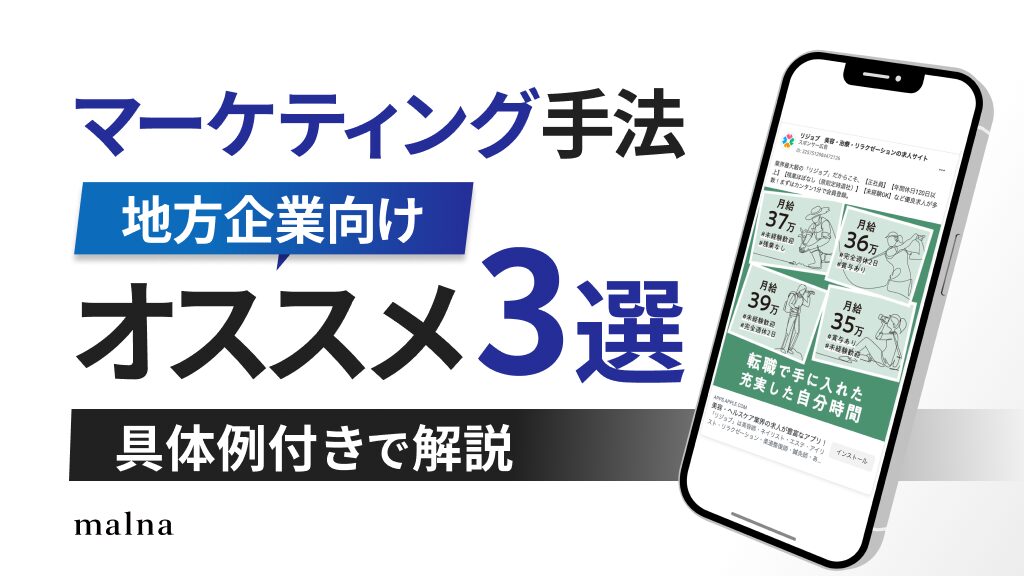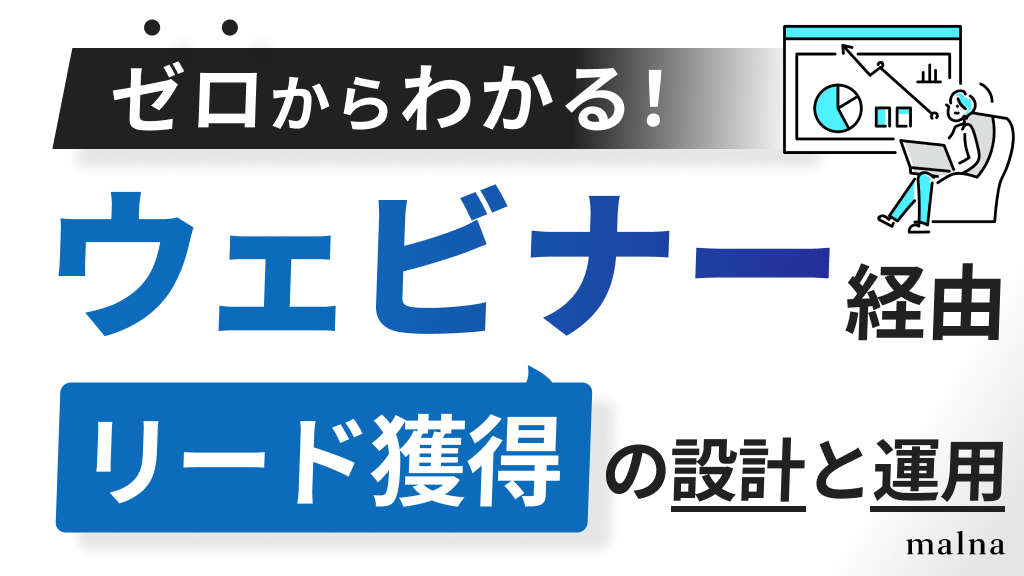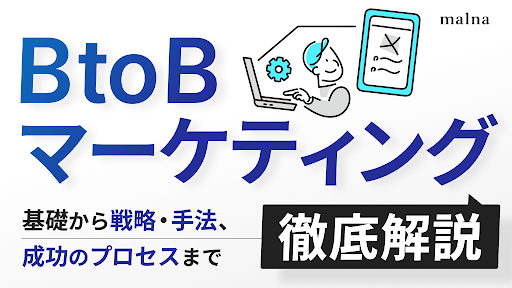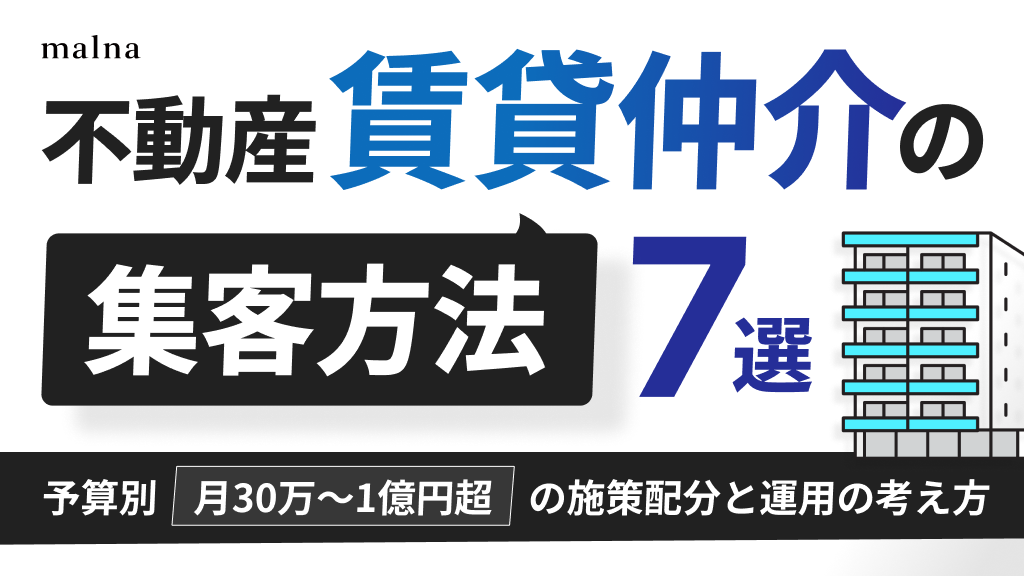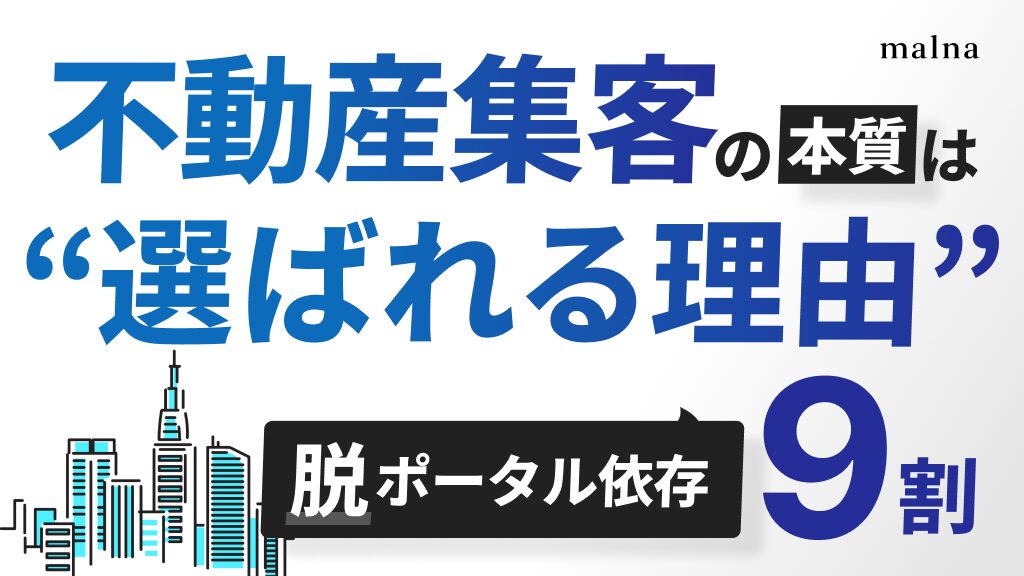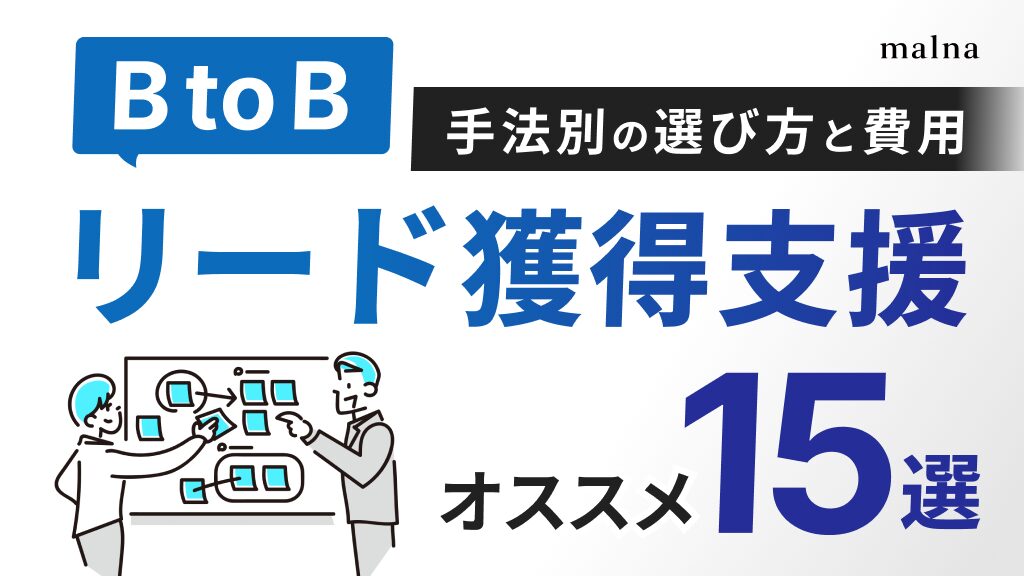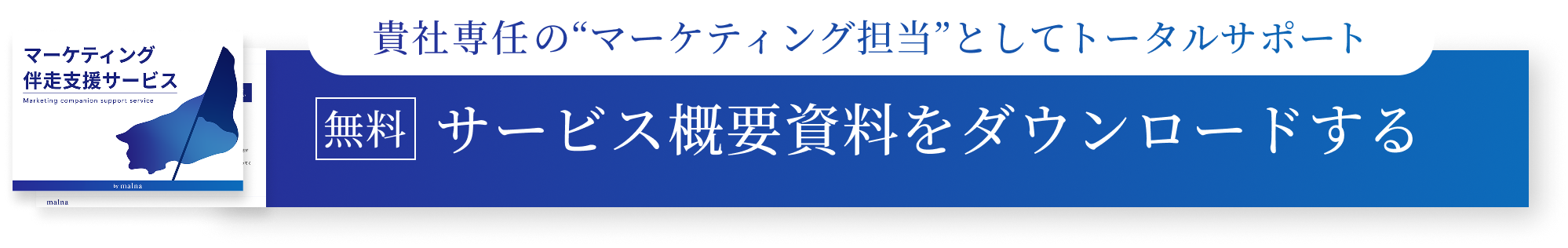2025.07.31
AIO対策とは?SEOとの違いや実践手順・メリットデメリットまで徹底解説
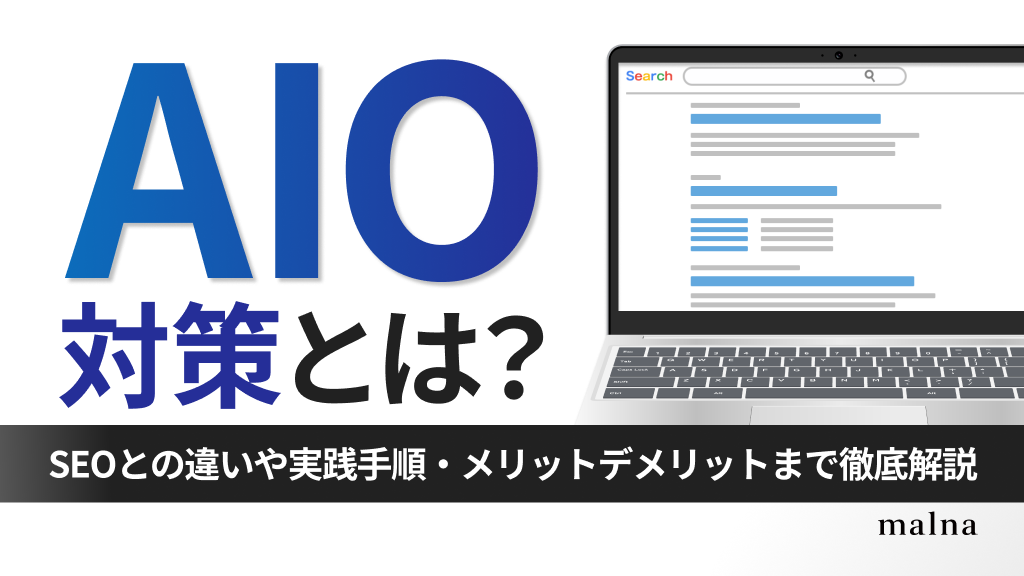
GoogleのAI生成検索やChatGPTなどのAI検索が当たり前になったことで、「AIにとってわかりやすい構造のコンテンツかどうか」が問われる時代が来ています。
そのなかで注目されているのがAIOという考え方です。
AIOは、「AI Optimization(AI最適化)」と「AI Overview(AIによる要約表示)」の双方に対応する設計を意味します。
本記事では、AIOの定義やSEOとの違いから始まり、AIOのメリットデメリット、成功させるための手順まで、わかりやすく整理しています。
AI探索に対応したいけど、何から始めればいいかわからないといった企業担当者の方に向けて、AIOをゼロから解説します。
AIO対策が注目されている理由
AI技術の進化によって、従来のように検索結果の一覧から自分で情報を探しにいく時代から、AIが瞬時に要約し、最適な情報を回答として提供する時代へとシフトしています。この変化にともない、検索結果で上位を取るだけでなく、AIに引用されることが、企業にとって新たな認知・集客のチャネルとなりつつあります。
AIOは、まさにその変化に対応するための考え方であり、いま多くの企業が注目し始めています。
AIOの定義と今注目されている理由
AIOは大きく2つの文脈で語られるようになっており、1つはGoogleのSGE(Search Generative Experience)で表示されるAI Overviewへの対応を意味します。ここでは、AIが生成する検索回答内に自社情報が引用されるよう、コンテンツの構造や表現を最適化することが求められます。もう1つは、ChatGPTやPerplexity、Geminiなどの生成AI検索全般におけるAI Optimizationという広義の意味です。
Google検索に限らず、あらゆるAIにとって読みやすく、信頼性のある一次情報として引用されやすくなるよう、コンテンツの構造化やE-E-A-Tの強化が重要視されます。いずれにおいても共通して重要なのは、AIが情報を正しく理解・要約できるように設計された構造を持っているかどうかです。いくら正確な情報を記載していても、見出しが曖昧だったり文脈が飛躍していたりすると、AIにとっては理解・引用しづらくなってしまいます。
こうした背景から、企業の情報発信戦略の中でも注目度が急速に高まっています。今後は、「検索で上位に出る」だけでなく、「AIに選ばれ、引用される」ことが、新たな競争優位性として鍵を握るようになるでしょう。
SEOとの違い
SEOは、人間の検索ユーザーがGoogleを使って情報を探す際に、上位表示されることを目的とした施策です。キーワード設計、内部リンク構造、被リンク施策、コンテンツ量と質などが評価軸となります。一方AIOは、AIが情報を読み取りやすくするために、構造化や文脈設計、FAQの明示といった観点で最適化を行います。検索ユーザーではなくAIを読者と見立てて設計するという点が、従来のSEOとは異なるポイントです。
AIO対策のメリット・デメリット
AI検索が主流となる未来において、AIOは企業にとって非常に有効な情報発信手段となります。しかし、どんな施策にもメリットとデメリットは存在します。ここでは、実際にAIOに取り組む前に押さえておきたいメリットとデメリットを整理します。
メリット
AIO対策に取り組むことは、単にAI検索への対応という側面にとどまらず、企業の情報発信全体を底上げする施策として非常に大きな可能性を秘めています。SEOと異なり、クリックされなくても表示が可能になるため、コンテンツの役割そのものが広がっていくと言っても過言ではありません。
1.AIに引用されることで、認知・信頼を築きつつ情報を直接届けることができる
生成AIの検索結果では、ユーザーがリンクをクリックしなくても、その場で情報が表示されます。そのときに引用されるコンテンツの筆頭が、自社のページであれば、たとえクリックに繋がらなくても、ブランド名やサービス名がAIによって紹介されることで、ユーザーの記憶に残る可能性は高まります。
従来のSEOでは得られなかったゼロクリックでの認知効果が得られるのが、AIOの最大の魅力です。特に検討初期フェーズの潜在層にも情報が届くため、長期的には今後の商談機会の創出にも繋がります。
2.E-E-A-Tや構造化を通じてコンテンツ品質が向上する
AIOでは、コンテンツがどれだけ“信頼できるか”が重要視されます。GoogleのE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を満たすこと、FAQやHowToなど構造が明確な形式にすることは、AIにとって理解しやすいだけでなく、読者にとっても読みやすく、分かりやすいコンテンツにつながります。
その結果、AIからの引用率だけでなく、ユーザーからの評価や滞在時間、コンバージョン率の向上にも好影響を与える可能性があります。AIOを意識することは、あらゆる面でコンテンツの質の向上に繋がります。
3.検索トレンドに先んじた施策で競合との差別化を図れる
まだ多くの企業がAIOに本格対応できていない中、いち早くAIに理解される構造を整えることで、競合よりも検索面で優位に立つことができます。これは、SEOのように検索順位で競うだけでなく、情報のわかりやすさから自社のコンテンツが取り上げられる可能性があるということです。
特にBtoB領域では、専門性や一次情報を保有している企業こそ、AIに引用される可能性が高く、先行者利益が得やすい状況にあります。いま動き出すことで、今後のAI検索市場での主導権を握ることも十分可能です。
デメリット
一方で、AIOにはいくつかのデメリットや気をつけるべきポイントもあります。本コンテンツでは、AIOを始める上で把握しておくべきAIOのデメリットについて解説します。
1,設計や構造化、E-E-A-T構築には手間と時間がかかる
AIOに取り組むには、従来のSEO記事作成でも必要とされている、FAQ構成、著者情報の整備などを徹底的に行う必要があります。また、組織としてE-E-A-Tを高めるには、専門家監修体制や著者ページの設置、情報の透明性を保つ更新フローなど、社内体制の構築が不可欠です。すぐに効果を出すことが難しく、地道な取り組みが必要になります。
2.成果が見えづらく、AIの仕様変更に影響されやすい
AIOの難しさの一つが、成果を数値化しにくいという点です。SEOであれば検索順位やクリック数が指標になりますが、AIOでは「AIに引用されたかどうか」を完全に追うのは困難です。また、GoogleやChatGPTなどAI側の仕組みが更新されるたびに、引用される条件や傾向も変わるため、継続的なモニタリングと柔軟な改善体制が求められます。
たとえば、FAQ構造が有効だった施策が、次のアップデートでは効果を失う可能性も否定できません。こうした変動性を前提としながらも、社内で「どこまで注力するか」「どのようにPDCAを回すか」を明確にすることが、AIO成功の鍵となります。
AIO対策を成功させる4ステップ
AIOはやったほうがよいと理解していても、実際に何から手をつければいいのか分からない方も多いのではないでしょうか。ここでは、初めて取り組む方でも実践しやすいように、AIO対策を進めるための4つの基本ステップを具体的に解説します。
ステップ①:現状の課題と目的を明確にする
まず最初に行うべきは、自社コンテンツが現在AI検索にどう表示されているかの確認です。GoogleのSGEやChatGPTに自社名やサービス名、想定される質問で問いかけてみましょう。自社サイトが引用されていない、あるいは意図しない内容が出てくる場合、構造の不備やE-E-A-Tのどれかが欠けていることが原因かもしれません。
そのうえで、「誰に何を伝えたいのか」「AIにどう引用されたいのか」といった目的を言語化しておくと、コンテンツ制作の方針がぶれにくくなります。
ステップ②:構造化コンテンツの設計・整備する
AIが引用しやすい構造に整えるには、コンテンツそのものの設計から見直す必要があります。具体的には、PREP法(結論→理由→具体例→再主張)やFAQ形式、HowTo構成などを活用しながら、AIが「質問→回答」の形で情報を抽出しやすい設計にします。
また、構造化マークアップ(Schema.org)によってFAQやHowToの情報を明示的に記述することで、AIが正しく理解・処理できるようになります。
ステップ③:E-E-A-Tと一次情報をなるべく採用する
AIOにおいて最も重視されるのが、情報の信頼性です。誰が書いたのか(著者情報)、どんな根拠があるのか(一次情報・出典)、監修がされているのか(専門家の関与)などを明記しましょう。たとえば、医療や金融、不動産などの専門性が高いテーマでは、実際に資格を持つ人物が執筆・監修したことを明示するだけでAIからの信頼度が大きく変わります。
一次調査データや社内レポートを引用することで、他社と差別化しやすくなります。
ステップ④:AI検索での引用状況をモニタリングする
施策を実行したら終わりではありません。定期的にAI検索結果を確認し、自社の情報がどのように引用されているかを把握しましょう。GoogleのSGE表示や、ChatGPT・Perplexityへのプロンプトによる確認が有効です。
また、引用された文脈や表現の傾向を記録しておくことで、今後のコンテンツ改善にも役立ちます。検索アルゴリズムやAI仕様は変化するため、PDCAサイクルを前提とした柔軟な運用が求められます。
AIOで評価されやすい4つのポイント
AIに引用されやすくなるには、信頼性の高い情報設計が欠かせません。本章では、AIOにおいて特に重要な4つのポイントを紹介します。コンテンツの本質的な価値を高め、AIが「この情報は正確で信頼できる」と判断するための基盤となります。
1. E-E-A-Tを意識したコンテンツを制作する
AIに評価されるためには、E-E-A-Tの要素が欠かせません。たとえば、「誰が書いたのか」「その人はどんな専門性を持っているのか」「どのような経験に基づいて書かれているか」といった背景情報が、信頼性の裏付けになります。
専門家による監修や、自社の調査データ・事例などを掲載することが大切です。また、コンテンツごとにE-E-A-Tを明示的に示すパーツを入れることで、AIの理解を促進できます。
2. ファクトチェックと情報ソースを記載する
AIは信頼できる情報源を重視します。引用元や参考文献、統計データなどは必ず明記し、事実確認の取れた情報を提供することが重要です。たとえば、「2025年●月の●●省発表データ」など具体的な出典を記すことで、コンテンツの透明性が高まります。
また、第三者機関のデータや学術情報などを交えると、AIによる信頼評価の底上げが期待できます。
3. 人間の手を入れる
生成AIによる文章は便利ですが、一方で「人間らしさ」が欠けてしまうことがあります。トーンの調整、読者の理解を助ける図解や余白の設計、語尾の多様性など、人間ならではの視点を加えることで、読み手にとって自然で信頼性の高いコンテンツとなります。特に、文脈や業界トレンドに寄り添ったニュアンスは、人の手による調整が不可欠です。
4. 読者ニーズに基づいてコンテンツを制作する
AIは「この検索クエリに最も適した情報は何か?」を常に評価しています。そのため、読者が抱える疑問や課題を的確に捉え、それに対して一貫した答えを提示する構成が求められます。検索意図に応じてFAQを設けたり、課題別のセクションを用意することが有効です。さらに、検索キーワードと一致するタイトル・見出しを最適化することで、検索意図との整合性が高まり、AIにも明確に伝わる構造になります。
AIO対策で気をつけるべき3つのポイント
AIO対策は、構造化やE-E-A-Tなど、注意すべき要素が多岐にわたります。しかし、それらすべてに一律で取り組むことは、リソースが限られたチームにとってはなかなか難しいです。
しかも、どの施策も同じように成果が出るわけではありません。ここでは、「全部を完璧にやるのではなく、影響度の高い施策から優先的に着手する」という視点で、AIO対策を進める上での考え方を整理します。
AIOの構成要素は多いが、効果に差がある
AIOで効果を出すためには、構造化マークアップ、E-E-A-Tを意識したコンテンツ設計、一次情報の追加、FAQ設計、HowTo整理、専門家による監修、著者プロフィールの記載、引用元の明示など非常に多くの要素があります。しかし現実には、それぞれの施策がもたらす影響度は異なります。
たとえば、医療や法律、金融などの領域ではE-E-A-Tの整備がAIに引用される鍵となりますが、BtoC向けのライフハック系やHowTo系コンテンツでは、FAQ構造や見出しの明確化の方が引用に直結しやすいケースもあります。つまり、「AIO施策を網羅する」ことではなく、「自社にとって影響の大きい部分から着手する」ことが成功の近道なのです。まずは、自社の業種や既存コンテンツの傾向を見直し、「何を優先すべきか」を判断する視点を持ちましょう。
工数がかかる施策は「続けられるか」で判断する
AIOは一過性の取り組みでは成果に結びつきません。たとえば、構造化マークアップを設定しただけ、E-E-A-Tを一度意識しただけでは、AIが継続的に引用してくれる保証はありません。むしろ、コンテンツの更新頻度や運用体制の方が評価に大きく関わってきます。そのため、継続的に維持・更新できる体制があるかを軸に施策を選ぶことが重要です。
以下は、取り組みにかかる負荷と継続性を示す施策の一例です。
これらをすべて同時に進めるのは非現実的です。まずは実行可能で効果が見込めるものから選び、PDCAを回せる体制で取り組むことが、成果への近道になります。
優先度を見極めてリソースを集中させる
AIO対策では、「やれること」ではなく「やるべきこと」に絞る視点が重要です。すべての施策に取り組むのは現実的ではないため、まずはAI検索での自社の表示状況を確認し、「どこを整えれば引用される可能性が高いか」を見極めましょう。たとえば、FAQがよく表示される分野であれば、FAQページの整備を優先すべきです。
著者の信頼性が重視される業界であれば、専門家による監修体制や著者情報の明示が有効です。サービスページに一次情報が不足しているなら、自社データの追加が差別化につながります。限られたリソースを最大限に活かすには、自社にとってインパクトの大きい領域に集中して取り組むことが、AIO成功の近道です。
まとめ
AIOについて解説しましたが、実際には、AIOで求められていることの多くは、従来のSEOで本来やるべきだった施策の延長線上にあるというのが実情です。
たとえば、E-E-A-Tの強化、FAQやHowToによるコンテンツの整理、著者や監修者情報の明示、一次情報の提示などは、SEOにおいても極めて重要な施策でした。
つまり、AIOとは単なるAI対応ではなく、「SEOの本質をどこまで真剣に取り組めているか」という点が非常に大事です。AIに正しく理解され、選ばれるコンテンツを作るということは、結局のところユーザーにとっても信頼性が高く、わかりやすいコンテンツであることを意味します。
AIOという言葉に振り回されるよりも、まずは自社のSEO施策がどれだけ“本質的にできているか”を見直しましょう。とは言え、AIOには非常に多くの工数とリソースがかかるため、自社にとって優先順位の高い施策を見極め、実行していくことが重要です。また、そのような状況では、リソースの配分も非常に重要になってくるので、運用体制の見直し、整備も同時に行っていきましょう。malnaでは、これまで数多くのBtoB企業のSEO支援を行ってきました。
「AIOにどう取り組むべきか悩んでいる」「そもそも今のSEOが本質的にできているか不安」「自社のリソースをどのように活用すれば良いかわからない」といったお悩みを抱えている方は、ぜひお気軽にmalnaへご相談ください。自社にあった運用体制の整備から、AIO対策にも通ずる本質的なノウハウまでお伝えします。
無料相談はこちら 記事一覧はこちら- malnaのマーケティングについて
-
弊社ではメディアやSNSなど総合的な支援が可能です。
媒体ごとに違うパートナーが入ることもなくスピーディな意思決定が可能です。
ご不明点や不安な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 - サービス資料はこちら 詳しく見る