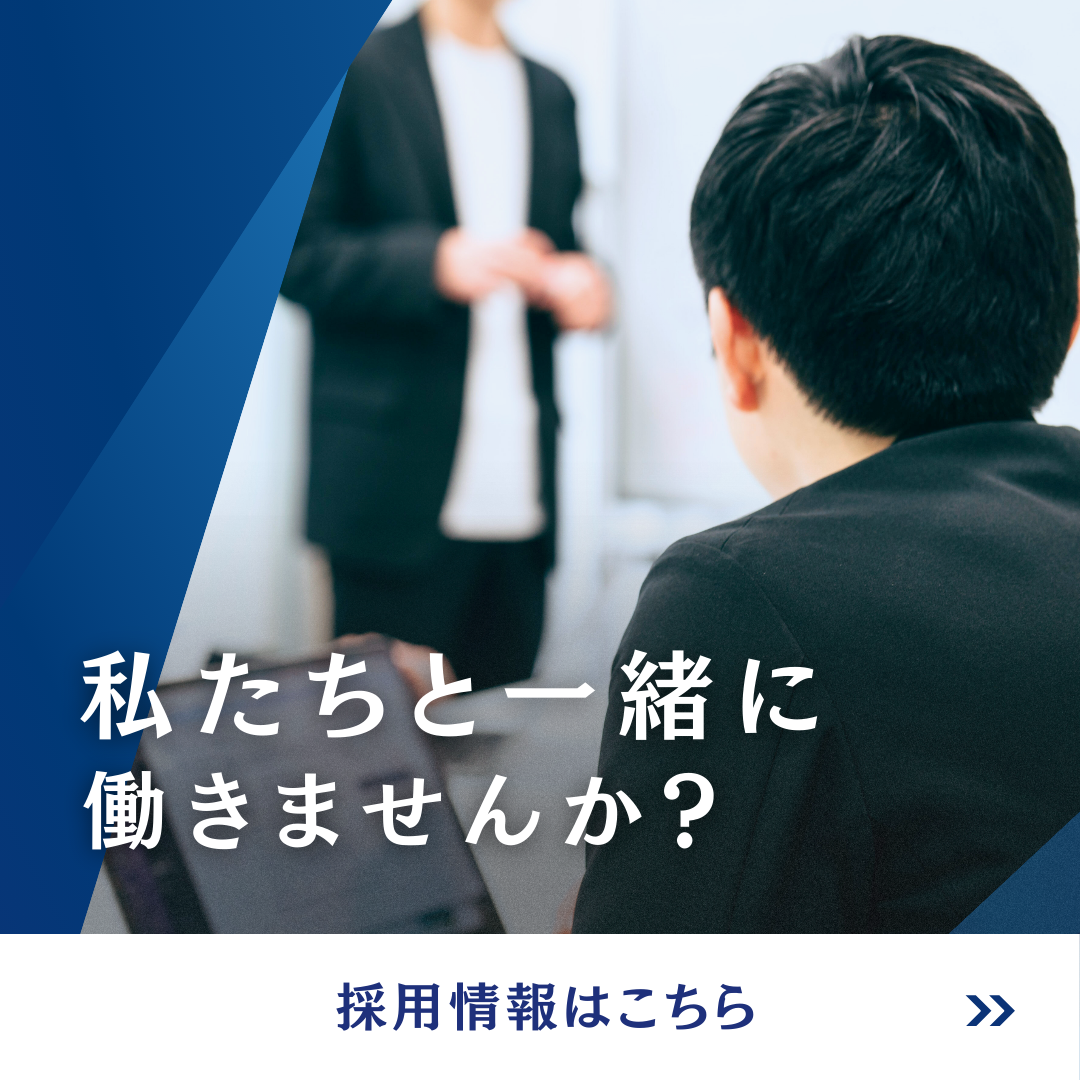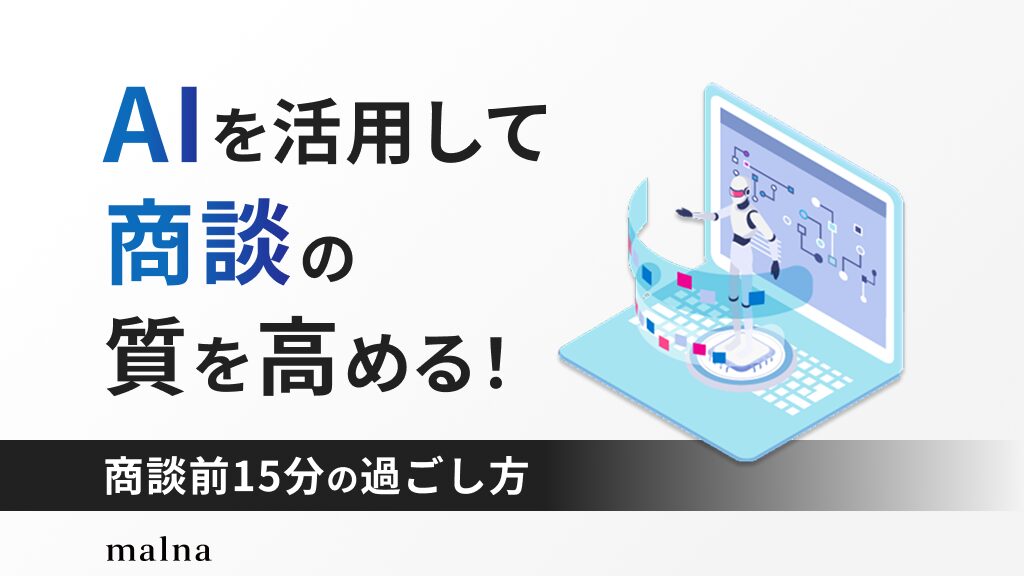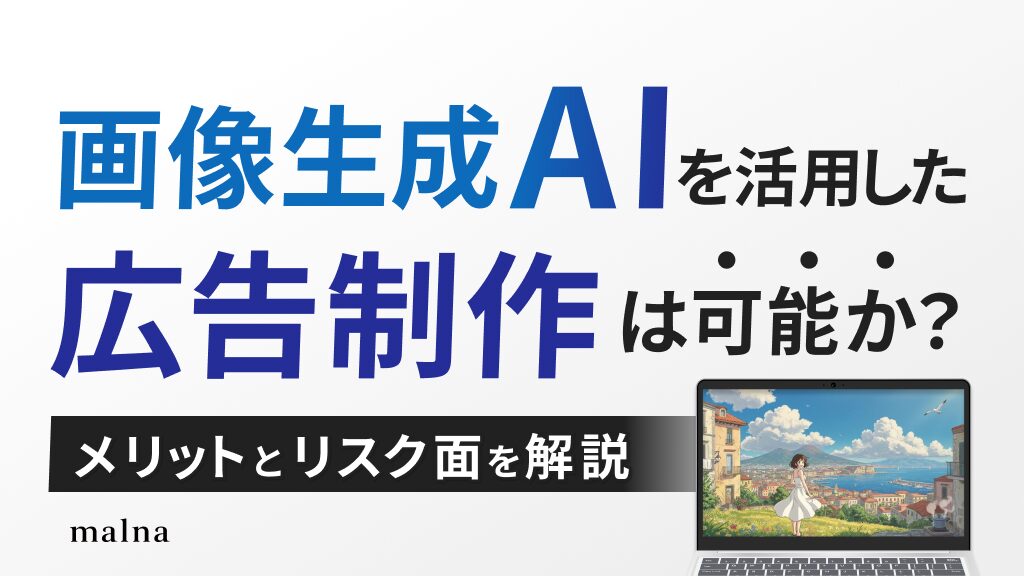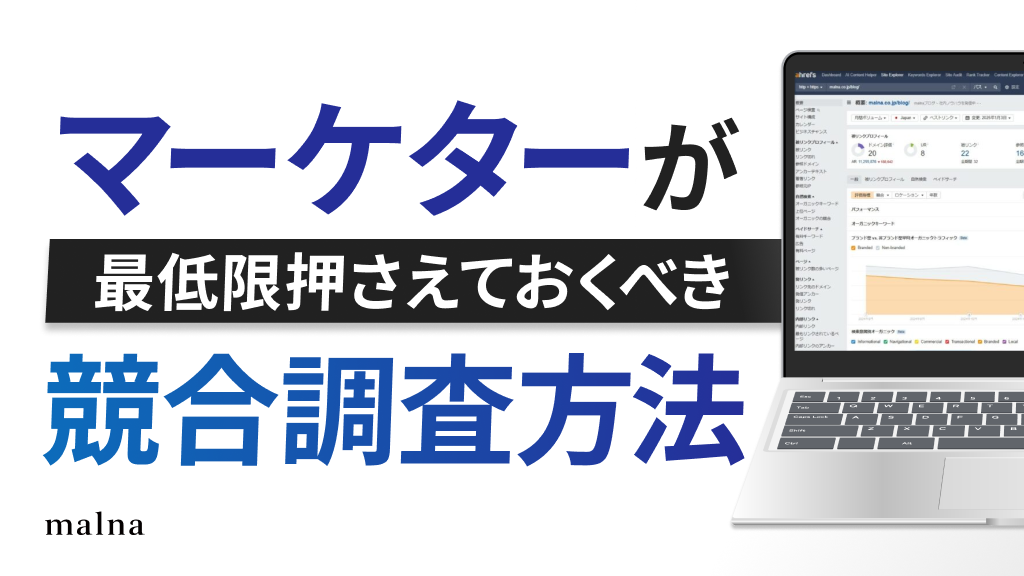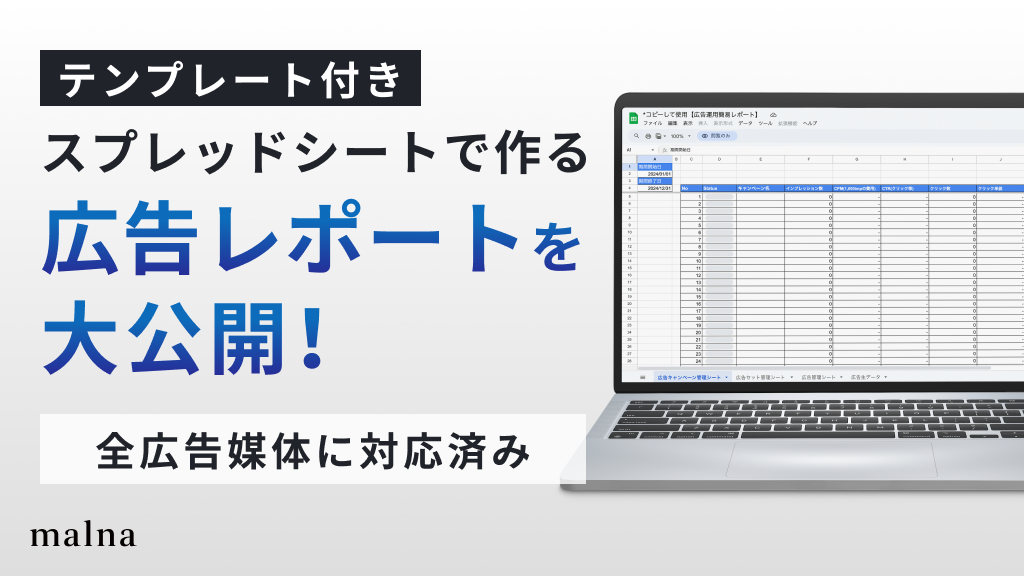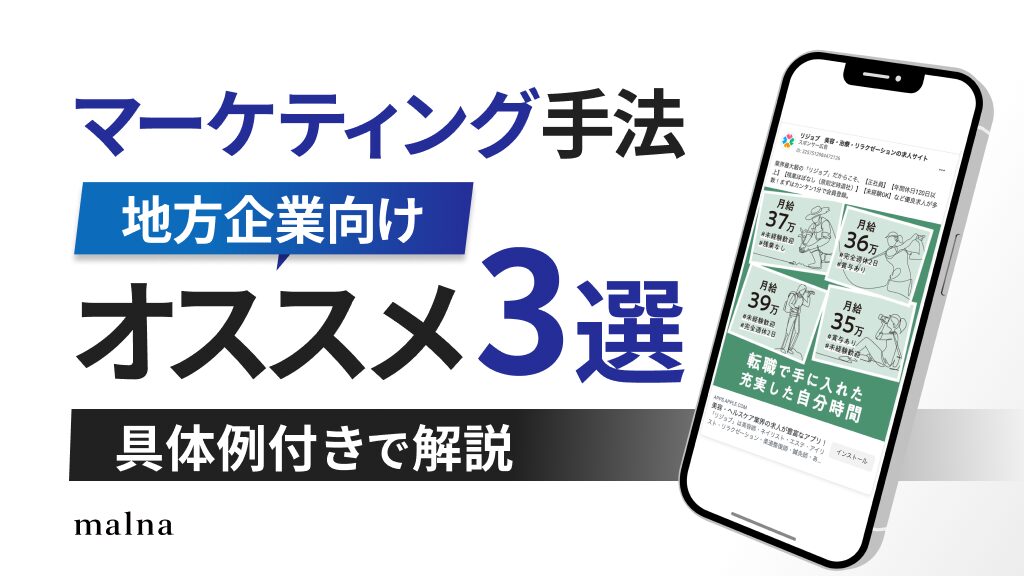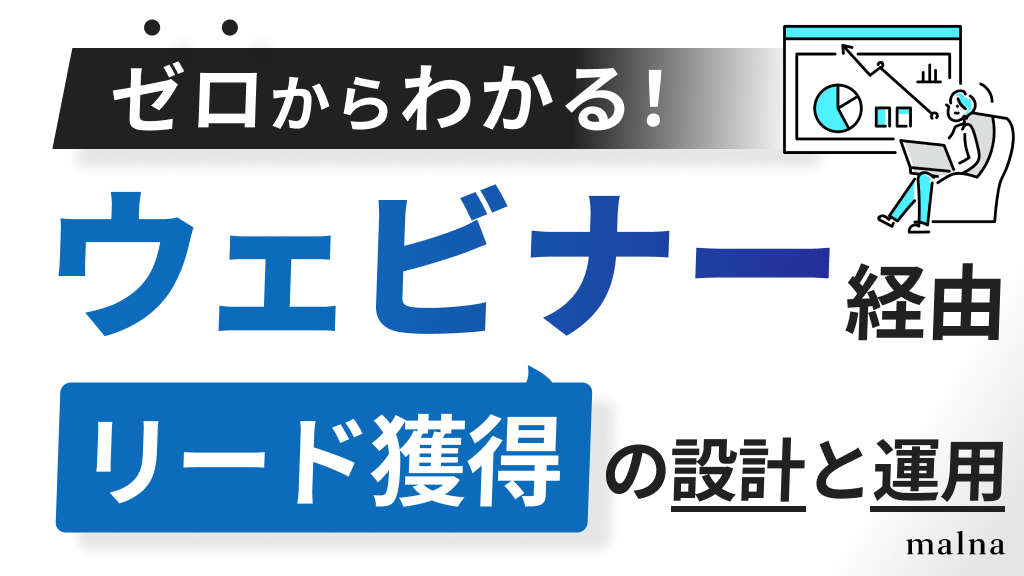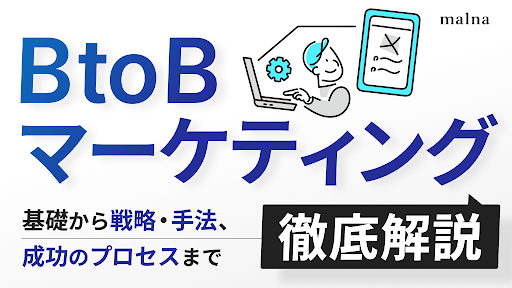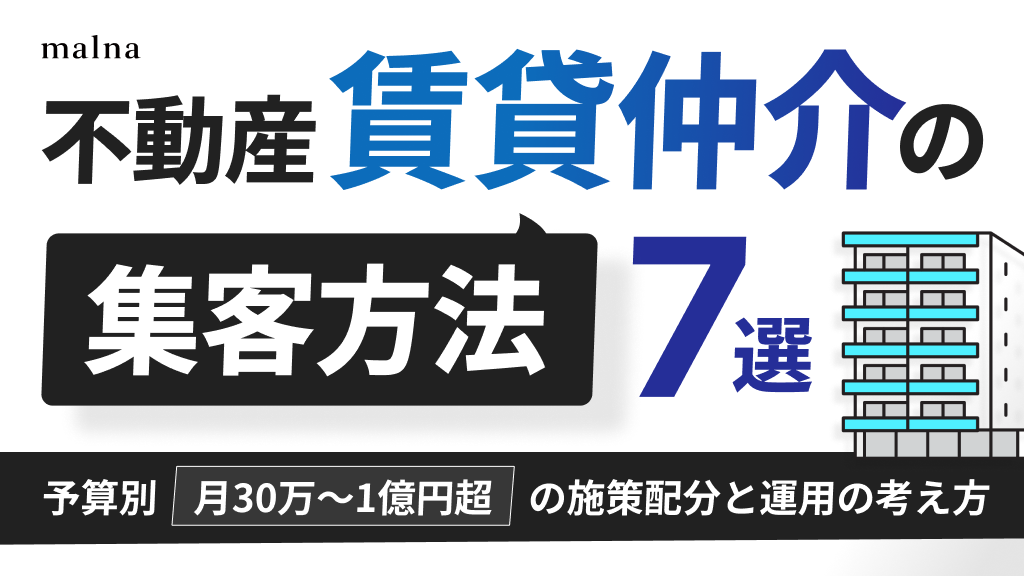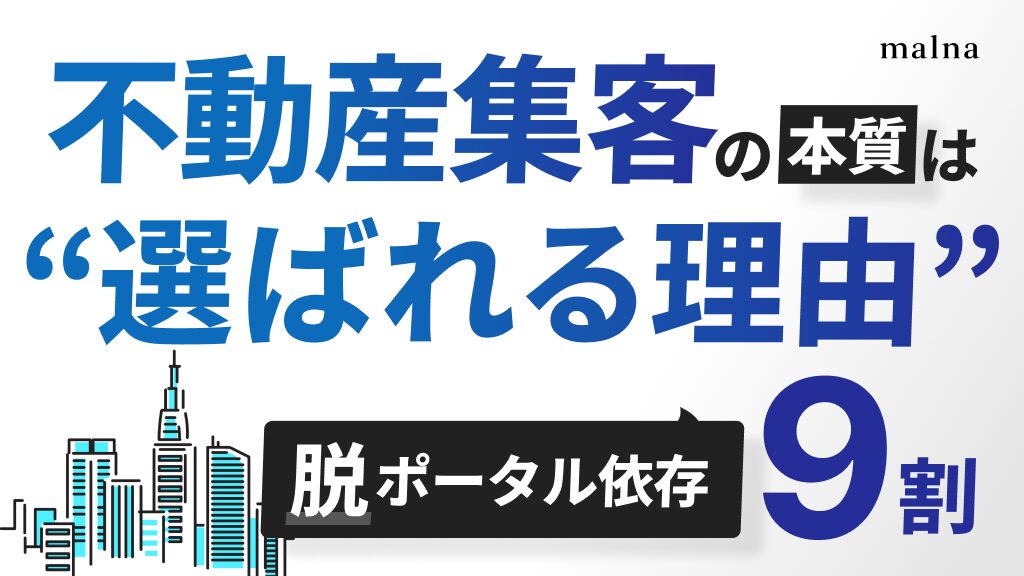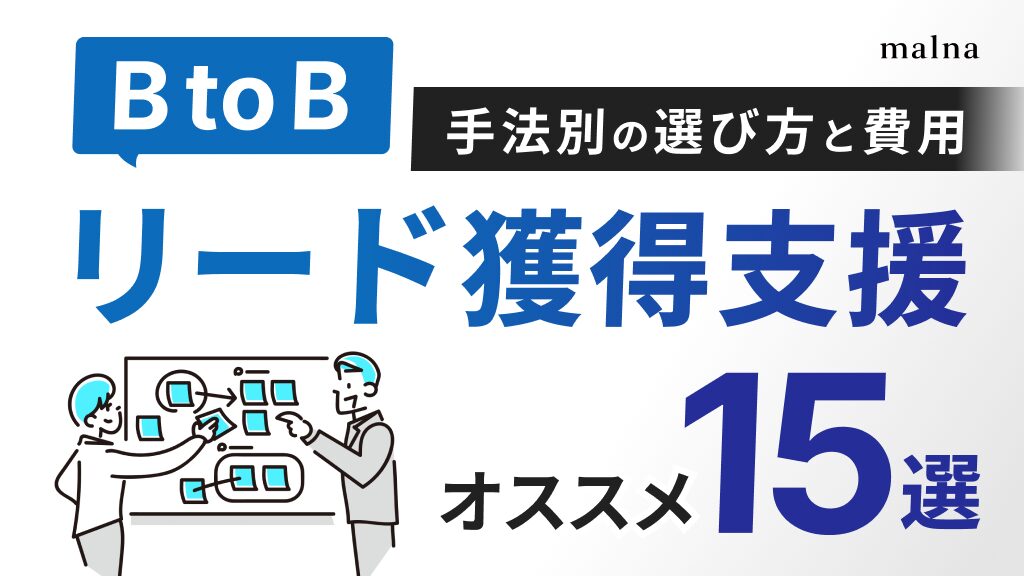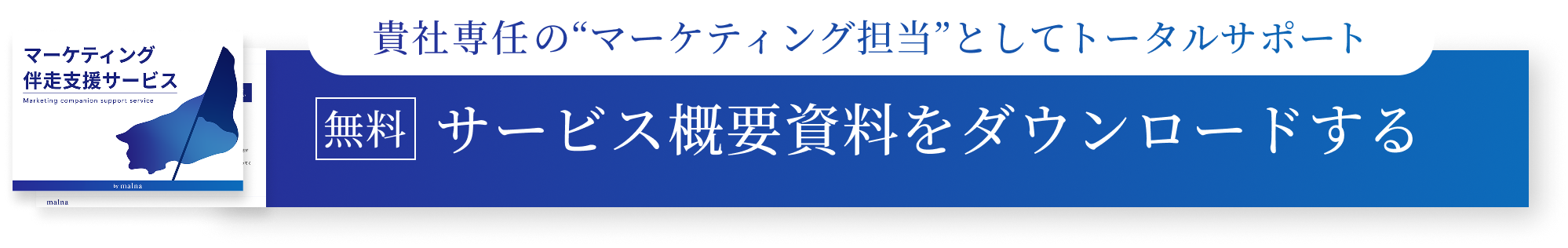2025.07.31
AIOとは?生成AI時代のSEO最適化戦略と実践ステップを解説

近年、Googleの検索結果は大きく変わりつつあります。従来のように上位10件のリンクが並ぶ検索画面は姿を消しつつあり、AIによる要約やチャット形式の回答が主流になっています。いわゆる「ゼロクリック検索」が当たり前になってきました。
こうした変化に対応する新たな考え方がAIOです。AIOは、生成AIに自社コンテンツを正しく理解され、適切に引用されることを目指す情報設計のアプローチで、具体的には、「AI Optimization(AI最適化)」と「AI Overview(AIによる要約表示)」の双方に対応する設計を意味します。
もはや「SEOだけでは足りない」と感じ始めている方にこそ、知ってほしい考え方です。
本記事では、AIOの基本的な定義から、SEOやAEO等との違い、実務に落とし込むための具体的な施策や成功ステップまでを、わかりやすく解説していきます。 「AIに読まれるコンテンツ」を作るための第一歩として、ぜひご活用ください。
AIOとは?
AI検索や生成AIの普及により、従来の検索表示とは違う表示がされる中で、注目を集めているのがAIOです。これはAIにとってわかりやすく、引用しやすいコンテンツを設計する考え方であり、多くの企業が注目し始めています。
AIOの定義と今注目されている背景
AIOは大きく2つの文脈で語られるようになっており、1つはGoogleのSGE(Search Generative Experience)で表示されるAI Overviewへの対応を意味します。ここでは、AIが生成する検索回答内に自社情報が引用されるよう、コンテンツの構造や表現を最適化することが求められます。
もう1つは、ChatGPTやPerplexity、Geminiなどの生成AI検索全般におけるAI Optimizationという広義の意味です。Google検索に限らず、あらゆるAIにとって読みやすく、信頼性のある一次情報として引用されやすくなるよう、コンテンツの構造化やE-E-A-Tの強化が重要視されます。
いずれにおいても共通して重要なのは、AIが情報を正しく理解・要約できるように設計された構造を持っているかどうかです。いくら正確な情報を記載していても、見出しが曖昧だったり文脈が飛躍していたりすると、AIにとっては理解・引用しづらくなってしまいます。こうした背景から、企業の情報発信戦略の中でも注目度が急速に高まっています。
今後は、「検索で上位に出る」だけでなく、「AIに選ばれ、引用される」ことが、新たな競争優位性として鍵を握るようになるでしょう。とは言え、AIOは新しい概念なので、「SEOで十分」「成果が測れない」といった意見も多く聞かれます。実際、AIOは意味がないのか、意味のあるAIOとは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。
まだ、AIOに取り組む意義がわからない、AIOに取り組むメリットをしっかりと把握してから施策に取り組みたいという方は、ぜひご覧ください。意味があるという側の意見と、意味がないという側の意見の両方からAIOとは何か、AIOに取り組む意義とは何かについて詳しく解説しています。
AIOは本当に意味ない?SEOとの違いやメリットなどを徹底解説
従来のSEOとの違い
SEOは、人間の検索ユーザーがGoogleを使って情報を探す際に、上位表示されることを目的とした施策です。キーワード設計、内部リンク構造、被リンク施策、コンテンツ量と質などが評価軸となります。一方AIOは、AIが情報を読み取りやすくするために、構造化や文脈設計、FAQの明示といった観点で最適化を行います。検索ユーザーではなくAIを読者と見立てて設計するという点が、従来のSEOとは異なるポイントです。
SEO・AEO・GEO・LLMOとの違い
SEO、AEO、GEO、LLMOといったさまざまな最適化手法が登場する中で、AIOはそれらを包括的にとらえる新しい戦略として注目を集めています。本章では、それぞれの最適化の特徴とAIOとの違いを明らかにし、今後のコンテンツ設計にどのように生かせるかを整理していきます。
- SEO(Search Engine Optimization):Googleなどの検索エンジンで上位表示されるためのコンテンツ設計。キーワード、内部リンク、被リンク、ページ速度、モバイル対応など、検索エンジンの評価アルゴリズムに合わせた技術的施策やコンテンツ改善が中心です。
- AEO(Answer Engine Optimization):音声検索やナレッジパネルなどに代表される”質問に対する回答”を目的とした最適化。FAQセクションを追加するだけでも、設問設計・回答文の調整・スキーマ適用など、複数の工程が必要です。
- GEO(Generative Engine Optimization):Google SGEやPerplexityのような生成AI検索が扱う情報の最適化。文脈理解、情報網羅性、構造の明快さなどが評価されやすく、従来のSEOとは別軸での工夫が求められます。
- LLMO(Large Language Model Optimization):ChatGPTやGeminiといったLLM(大規模言語モデル)に理解・引用されることを前提に設計する手法。会話形式において自然な回答として扱われるためには、明確なファクト、ナレッジベース化、E-E-A-Tなどが不可欠です。
AIOとの違い
AIOは、AIに引用されることを前提としたコンテンツ設計全般を指します。GEOやLLMOなど他の最適化手法は、生成AIやLLMごとの技術要件に特化していますが、AIOはそれらを包括し、AIが信頼できる情報として扱える構造や内容を整える設計を意味します。一言で言えば、AIOとは“AIに選ばれるためのコンテンツ最適化です。
AIO施策を成功させるための4ステップ
AIO施策を効果的に進めていくには、体系立てたプロセスが必要です。ここでは、実務で活用できる4ステップを紹介します。コンテンツの価値をAIに正しく伝えるための「設計・実装・検証」の流れを意識して取り組むことが重要です。
ステップ1:現状の課題を洗い出す
まずは、自社コンテンツの現状を可視化しましょう。構造が論理的か、見出しや段落が整理されているか、FAQや図表など情報補足があるかといった「読みやすさ」を軸にチェックします。 また、E-E-A-Tの観点から、信頼できる一次情報や情報源の明記、著者情報の提示、専門家による監修の有無など、AIが評価しやすい信頼性の指標も洗い出しましょう。さらに、網羅性も重要です。「このトピックに関するすべての要素がそろっているか?」を確認し、他社と比較して弱い部分を明確にします。
ステップ2:コンテンツを再設計する
課題が見えたら、AIにとって「読みやすく信頼できる構造」へとコンテンツを再設計していきます。FAQやHowToといった、直接的な回答型セクションを盛り込むことで、AIが抽出しやすい形になります。 E-E-A-T(専門性・経験・権威性・信頼性)を体現するためには、著者プロフィールや企業の実績データ、監修者の肩書き・所属を記載し、情報の裏付けを明記することが求められます。 また、コンテンツ自体の文体も自然で、論理的に構成されているか見直し、不要な冗長表現を削減しながら精度を高めましょう。
ステップ3:構造化データ・タグ・マークアップを実装する
AIがコンテンツを理解するうえで、構造化データは非常に重要です。Schema.orgを活用し、Webページの各要素に意味づけを行うことで、情報を明確に伝えることができます。 具体的には、FAQPageやHowTo、Article、Organization、Author、Productなど、該当するスキーマをページごとに設定しましょう。特にFAQPageスキーマは、GoogleのSGEや生成AIにおいて再利用される頻度が高いため、優先的に実装したい項目です。 構造化マークアップに加えて、適切なタイトルタグ・見出しタグ(h1〜h3)も併せて最適化し、情報の階層性を明確にすることが重要です。
ステップ4:AI検索での露出を検証・改善する
施策を実施した後は、実際にAIに引用されているかを定期的にチェックしましょう。GoogleのSGEにおけるサマリー表示や、ChatGPT・Geminiなどが出力する情報に自社の内容が反映されているかを確認します。 直接的な流入やCTRではなく、「引用の有無」「引用された文脈」「出典の扱われ方」といった視点でモニタリングし、必要に応じてFAQの追加、見出しの改善、スキーマの追加など細かな最適化を継続します。 AIOは一度で完了するものではなく、PDCAをまわしながら継続的に改善を重ねるアプローチが求められます。
AIOで評価されるために抑えるべき4つのポイント
AIに引用されやすくなるには、信頼性の高い情報設計が欠かせません。本章では、AIOにおいて特に重要な4つのポイントを紹介します。コンテンツの本質的な価値を高め、AIが「この情報は正確で信頼できる」と判断するための基盤となります。
1. E-E-A-Tを意識したコンテンツ制作
AIに評価されるためには、E-E-A-Tの要素が欠かせません。たとえば、「誰が書いたのか」「その人はどんな専門性を持っているのか」「どのような経験に基づいて書かれているか」といった背景情報が、信頼性の裏付けになります。専門家による監修や、自社の調査データ・事例などを掲載することが大切です。また、コンテンツごとにE-E-A-Tを明示的に示すパーツを入れることで、AIの理解を促進できます。
2. ファクトチェックと情報ソースの明記
AIは信頼できる情報源を重視します。引用元や参考文献、統計データなどは必ず明記し、事実確認の取れた情報を提供することが重要です。たとえば、「2025年●月の●●省発表データ」など具体的な出典を記すことで、コンテンツの透明性が高まります。また、第三者機関のデータや学術情報などを交えると、AIによる信頼評価の底上げが期待できます。
3. 人間による編集
生成AIによる文章は便利ですが、一方で「人間らしさ」が欠けてしまうことがあります。トーンの調整、読者の理解を助ける図解や余白の設計、語尾の多様性など、人間ならではの視点を加えることで、読み手にとって自然で信頼性の高いコンテンツとなります。特に、文脈や業界トレンドに寄り添ったニュアンスは、人の手による調整が不可欠です。
4. 読者ニーズに基づいたコンテンツ制作
AIは「この検索クエリに最も適した情報は何か?」を常に評価しています。そのため、読者が抱える疑問や課題を的確に捉え、それに対して一貫した答えを提示する構成が求められます。検索意図に応じてFAQを設けたり、課題別のセクションを用意することが有効です。さらに、検索キーワードと一致するタイトル・見出しを最適化することで、検索意図との整合性が高まり、AIにも明確に伝わる構造になります。
AIOのメリットとデメリット
AIOはこれからのコンテンツ設計において非常に重要な考え方ですが、その導入には利点と注意点の両方があります。ここでは、AIOに取り組むことで得られるメリットと、実施に際してのデメリットを整理し、自社にとっての導入判断の材料として活用できるようにまとめます。
メリット
以下では、AIOのメリットについて紹介しています。AIに引用されることで信頼性の向上やコンテンツの質の向上、競合との差別化といったメリットがあります。
認知・信頼を築きつつ情報を直接届けられる
ChatGPTやGoogle SGEなど、生成AIが検索体験の一部として浸透するなかで、AIに引用されることは新たな情報の露出機会となっています。たとえば、ユーザーが質問を投げかけた際、あなたのコンテンツがその回答の一部として表示されれば、検索結果をクリックしなくても、ブランドやサービス名が認知される可能性があります。これは従来のSEOでは得られなかった接触ポイントであり、信頼の構築において大きな武器になります。
E-E-A-Tや構造化を通じてコンテンツ品質が向上する
AIOの実践は、必然的にE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の強化と構造化マークアップの整備を求められるため、コンテンツ全体の品質が底上げされます。たとえば、「著者プロフィールの明記」「ファクトベースの情報設計」「FAQやHowToの充実」など、ユーザーにとっても有益で読みやすい構成になります。その結果、AIだけでなく検索エンジンやユーザーからの評価も高まり、総合的な集客力向上に繋がります。
検索トレンドに先んじた施策で競合との差別化を図れる
AIOはまだ実践企業が少ない分野です。だからこそ、いまの段階でしっかり取り組むことで、将来のAI検索が主流になった際に「引用されやすいポジション」を先取りできます。たとえば、同じ内容でもAIOに最適化されたコンテンツの方がAIに選ばれる可能性が高くなり、競合と同じ土俵に立ちながらも、検索面での差別化が可能です。
デメリット
一方で、AIOを実現するためには一定のリソースと継続的な取り組みが不可欠です。そのため、ハードルが高く感じられることや成果が見えづらいといったデメリットもあります。
設計や構造化、E-E-A-T構築には手間と時間がかかる
AIO対応を本格的に進めるためには、コンテンツの構成を見直すだけでなく、著者情報の整備、信頼ソースの明示、Schema.orgによるマークアップなど多岐にわたる作業が発生します。たとえば、FAQセクションを追加するだけでも設問設計、回答文調整、スキーマ適用など複数の工程が必要です。中小企業ではコンテンツ運用担当の負荷が大きくなりがちで、実行に向けた社内体制づくりが課題となるケースも少なくありません。
成果が見えづらく、AIの仕様変更に影響されやすい
従来のSEOでは、クリック率や流入数といった成果が比較的明確に見えましたが、AIOの場合「AIに引用されたかどうか」は可視化しにくく、成果の判断が難しいという側面があります。また、ChatGPTやGoogle SGEのようなAI検索は表示仕様が頻繁にアップデートされるため、今日の最適化が明日には無効になるリスクもあります。このように、不確実性を含む領域であることは、慎重なモニタリングと柔軟な改善運用を前提に考える必要があります。
AIO成果をどう測る?KPI設計とモニタリング指標
AIOの施策は、SEOのように検索順位やアクセス数だけで測るのは困難です。生成AIによる引用や回答形式が増える中、ユーザーの接触経路が多様化しているため、従来のKPIに加えて、AIOに特化した新たな評価指標が求められています。本章では、AI検索時代における代表的なモニタリング指標を紹介します。
AI検索での引用率・表示率
AIOの評価軸として注目されているのが「ACE指標」です。これは、Answer(AIに回答として表示されたか)、Citation(情報源として引用されたか)、Exposure(ユーザーに視認されたか)の3つの観点から、自社コンテンツがAIにどう扱われているかを定量・定性の両面で測定するものです。
たとえば、Google SGEで自社コンテンツがサマリーとして表示されているか、ChatGPTやGeminiなどで情報源として参照されているか、そしてその情報がユーザーの目に触れているかを観察します。引用の頻度や内容、表示された文脈、リンクの有無などを定期的に確認し、改善施策の検討材料とすることで、より効果的なAIOの実行につながります。
ゼロクリック率とブランド認知の計測
AIが回答して完結する「ゼロクリック検索」では、直接のクリック数だけでは効果を測れません。その代わりに、「ブランド名の検索数」「SNSや口コミでの言及数」「ユーザーからの指名問い合わせ」など、間接的な認知指標が重要になります。 たとえば、あるキーワードで自社がAIに引用された後に、同月の指名検索が増加していれば、AIOによるブランド浸透の成果と捉えることができます。これらの動向はGoogleトレンドやSNS分析ツールを使ってモニタリング可能ですAIO対策には一定の時間とコストがかかる
AIOは、成果につながる可能性がある一方で、短期的に簡単に実現できるものではありません。構造設計や専門性の担保、技術的対応など、複数の要素が絡み合うため、ある程度のリソースと時間が必要です。ここでは、AIOを無理なく行っていくために意識したい3つのポイントを紹介します。
1. すべての要素に一律対応するのは非現実的
AIOでは、構造化マークアップ、FAQ設計、著者情報の記載、一次情報の挿入、E-E-A-Tを意識した構成など、求められる要素が多岐にわたります。ただし、それらをすべて均等に実行するのは難易度が高く、リソース的にも厳しいというのが実情です。業界やコンテンツの種類によって効果の高い対策は異なるため、「まず何から始めるべきか」を見極めることが重要です。すべてを一斉に始めるのではなく、インパクトの大きい箇所に的を絞って進めることが、効率よく成果を上げるための基本戦略です。
2. 継続可能性を前提に設計する
一度設定しただけで効果が続く施策は少なく、多くの場合で運用や更新が求められます。施策ごとの導入時の負荷や、その後の維持にかかる労力をあらかじめ把握しておくことで、現実的に続けられる体制を作ることができます。以下の表は、主要なAIO施策について「初期工数」「継続工数」「特長」を比較したものです。
3. 自社にフィットする施策を選び抜く
限られたリソースの中で成果を出すためには、「やるべきこと」に絞って行動する判断力が重要です。施策の汎用性や業界特性をもとに、優先順位を見極めて取り組むことが成果への近道となります。たとえば、AIによるFAQ表示が多い業種では、FAQページの精度向上が直接的な効果を生みやすいです。
逆に、専門性や信頼性が重視される領域では、著者や監修情報の提示が強い武器になります。また、他社と差別化できる独自データの提示も有効な選択肢の一つです。重要なのは、「やれること」ではなく「やる意味があること」に集中することです。効果の見込める分野に優先的にリソースを配分することで、効率よくAIに引用される土台を築くことができます。
まとめ
AIOは目新しい概念のように見えますが、その本質は「SEOで本来取り組むべきだった重要な施策を、AIにも伝わるかたちでどれだけ徹底できるか」にあります。E-E-A-Tを意識した設計や構造化、検索意図に沿った情報設計といった基本的なSEOの取り組みを、AIに読み取られやすく再構成するのがAIOの核です。
とはいえ、AIOの施策は多岐にわたり、すべてに一律で対応するのは現実的ではありません。業種やマーケティングの目的によって、「AIからの引用を狙う意義」や「注力すべき施策の優先度」は変わってきます。たとえば、toBのナーチャリングを重視する企業であれば、E-E-A-Tや一次情報の整備に重点を置くべきです。
一方、toCの比較コンテンツでは、FAQ構造やページ表示の最適化がより効果を発揮します。つまり、AIOは「やれることを全部やる」施策ではなく、「目的に応じてやるべきことに絞る」施策です。限られたリソースの中で最大の成果を出すには、施策ごとのインパクトを見極め、優先順位をつけて進める視点が欠かせません。
もし、「SEOで成果を出したいが出せていない」「AIOに取り組みたいけど、自社のリソースをどう生かせばいいかわからない」といったお悩みを抱えている企業のマーケティング担当者は、malnaにご相談ください。malnaでは、SEOとAIOの両面から成果に直結するコンテンツ設計・運用の支援を行っています。
無料相談はこちら 記事一覧はこちら- malnaのマーケティングについて
-
弊社ではメディアやSNSなど総合的な支援が可能です。
媒体ごとに違うパートナーが入ることもなくスピーディな意思決定が可能です。
ご不明点や不安な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 - サービス資料はこちら 詳しく見る